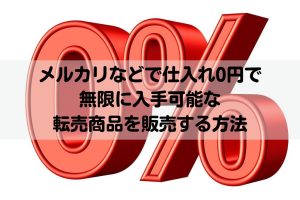リベートにかかる消費税の仕訳方法と値引・割戻・割引の区別
買い物をする時などに、よく目にしたり耳にしたりする値引や割引。
割戻(リベート)はそれほどなじみがないかもしれませんが、どれも正規の価格から引くというイメージがありますよね。
ただし会計上では、値引、割引、割戻(リベート)それぞれを区別して処理する必要があります。
そこで今回は、値引、割引、割戻(リベート)の意味、そしてこれらが関わる消費税の調整方法を詳しくご紹介します。
値引・割戻(リベート)・割引それぞれの意味

sale
値引・割戻・割引の3つは、似たような言葉で、商品などの物、またサービスの対価などに支払う代金を安くするという共通点があります。
ただし、それぞれ安くするための理由に違いがあります。
値引の意味
会計上で定義される値引とは、提供する商品などの物、サービスなどの「質」を理由にしてその代金を安くすることです。
質については、季節外商品、不良品、破損した品物といったものの他に、以下のようなものも当てはまります。
・展示品のため価格を下げる
・賞味期限が近い食品の価格を下げる、本日中に売る必要のある調理されたおかずの価格を下げる
・商品が入っている箱が破損してしまったので、中身には問題はないが価格を下げる
割戻(リベート)の意味
会計上で定義される割戻とは、提供される商品などの物や、サービスに関する「量」を理由に、値引きをすることです。
いわゆる「まとめ買い」がこれに当てはまります。
たくさん買う、まとめて買うことで価格を下げることをいいます。
スーツ量販店で3着購入したら1着無料、といったことから、ジュースを3本買うと1,200円を1,000円にする、といったことです。
電車やバスの回数券を買うと1回分無料になるのも割戻です。
割引の意味
会計上の割引の意味は、提供される商品などの物、サービスに対する代金を、あらかじめ決められている期限よりも早く支払うことで、安くすることです。
借りたお金を早く返してくれたら、それまでの利息分は安くしますよ、ということです。
ビジネスのやり取りだと、商品の仕入れで代金は毎月月末締めで、翌月の15日に支払いをすることになっているが、納品時に現金で支払う場合は商品代金から1割安くしますといったことが当てはまります。
値引の仕訳の方法

まずここでは値引の仕訳についてご紹介します。
値引きには、仕入れた商品の値引きをしてもらう「仕入値引」と、販売した商品を値引きする「売上値引」の2つがあります。
この2つの値引きは逆仕訳を使えるため、値引きの勘定科目を使わずに仕訳します。
仕入値引の仕訳方法
商品を仕入れる際に、先方から値引きしてもらったという場合、元々の仕入れの時の価格よりも安く購入できたということになります。
そのため仕訳の時には、値引きをしてもらった分を逆仕訳して、値引きされたことを明らかにする必要があります。
例として、15,000円の商品を仕入れ、3,000円値引きしてもらったとします。
まず、仕入れの仕訳は
仕入15,000/買掛金15,000
です。
今回掛けで仕入れていますが、支払う手段によって貸方の項目は変わります。
ここから値引きを仕訳します。
買掛金3,000/仕入3,000
値引きしてもらったことで、先に支払う予定だった買掛金が減ります。
売上値引の仕訳方法
売上値引の場合も、先ほどの仕入値引きと同じく、値引き分を戻す仕訳をします。
例えば20,000円で販売した商品を、5,000円値引きして販売したとします。
売掛金20,000/売上20,000
値引きを仕訳します。
売上5,000/売掛金5,000
値引きにより、先になって支払ってもらう予定だった売掛金が減ります。
値引きは返品の際の処理と同じ
簿記での値引き処理は、返品の際にする処理とよく似ています。
返品の時には、「仕入戻し」や「売上戻し」といい、仕入れをなかったことにする処理になります。
例えば3,000円で仕入れた商品が不良品だったので、全て返品することにしたとします。
買掛金3,000/仕入3,000
同じく3,000円で販売した商品が、品番違いで返品になったとすると、
売上3,000/売掛金3,000
となりますので、合わせて覚えておくといいでしょう。
割戻(リベート)の仕訳方法

割戻は、値引と違い、商品自体に問題があるわけではなく、たくさん仕入れてもらった際などに価格を安くすることです。
ビジネスの場合、契約している期間中にある一定量数以上の仕入れをしてもらった場合などに、その増加分に対し一律値引きをするといったことがあります。
仕訳については、値引のやり方と似ていますが、どう違うのか詳しくご紹介します。
仕入割戻(リベート)の仕訳方法
例えば、ある卸問屋と1,000円の商品を毎月100個買い掛けで仕入れる契約をしていましたが、支払い当日に1割引にしてもらったとします。
この仕訳をしてみましょう。
まず仕入れについてですが、
仕入100,000/買掛金100,000
そして今回は1割引で売りましょう、と買掛金を支払う時に言われたとします。
現金で実際に支払った金額を仕訳すると、
買掛金90,000/現金90,000
となりますが、そうすると買掛金が10,000円、負債のまま残っています。
そのため、ここでは「割戻してもらった」という仕訳を記入する必要があります。
正しくは、
買掛金100,000/現金90,000
買掛金(もしくは仕入戻し)10,000
これで買掛金は0になり、現金に加え、割戻があったことが分かります。
売上割戻(リベート)の仕訳方法
今度は売り手側の方から仕訳をしてみましょう。
1,000円の商品を100個掛けで販売していますから、
売掛金100,000/売上100,000
となります。
売掛金を回収時に1割引として支払ってもらいますので、
現金90,000/売掛金100,000
売掛金(もしくは売上割戻)10,000
となり、実際には1割引いたと分かります。
勘定科目はどちらを使ってもいいの?
割戻の仕訳処理として、買掛金も売掛金もそれぞれを割戻の勘定科目として使っても問題はありません。
ただし値引きの際の仕訳と処理が同じになってしまいますので、「どういった内容でこの処理は行われたのか」を明らかにするためには、仕入れ割戻や売上割戻を勘定科目として使う方が分かりやすくなります。
損益計算書でその点が確認できるためですが、値引きも割戻もどちらの処理もする場合は、使い分けるといいでしょう。
割引の仕訳方法

割引の処理については、割戻と似ているのですが、内容が異なるため注意が必要です。
仕入割引の仕訳方法
商品を50,000円分掛けで仕入れ、支払いは2ヶ月先にするという契約を交わしました。
この場合の仕訳は、
仕入50,000/買掛金50,000
となります。
買掛金の支払いは2ヶ月後という契約でしたが、まとまった売上があり、早めに支払うことが可能になったので、先方にそれを伝えたところ、「早く支払ってくれるなら1割引しましょう」という話になりました。
これが割引ですね。
実際に仕訳してみましょう。
買掛金50,000/現金45,000
この場合、仕入割引という勘定科目を使用します。
買掛金50,000/現金45,000
仕入割引 5,000
これで割引してもらった分も明らかになります。
売上割引の仕訳方法
この割引を、今度は割引した方から見て仕訳してみましょう。
売掛金50,000/売上50,000
支払期日は2ヶ月後でしたが、先方から早めに支払いができるとのことだったので、1割引きをして現金で受け取りました。
現金45,000 /売掛金50,000
売掛値引き5,000
これで割引したことが明らかになりました。
割戻(リベート)と割引は別物!違いと仕訳方法を確認しよう
割戻は、たくさん購入した、まとめて買ったときなどに発生する処理のこと。
割引は支払期日より早く支払うことで発生する処理です。
大まかにはどちらも割引なのですが、内容は異なります。
そのため仕訳で分けることで、何があって割り引きされているのかが明らかになります。
きちんと使い分けることで、仕訳をスムーズに行うことができるようになります。
こちらに不手際があったのか、また相手に不備があったのかも、ここで確認できますので、きちんと行うようにしましょう。
消費税申告とは?対象者や申告について知っておこう

ビジネスを行っていて、ある程度の売上をあげるようになってきたら、消費税を支払った、もしくは受け取ったことを税務署に申告する義務が発生します。
ここでは消費税の仕組みや、納税の義務の有無についての確認の仕方などを詳しくご紹介します。
消費税はどんな仕組みになっているの?
消費税とは、商品の購入やサービスを受けた時に発生する税金のことをいいます。
商品を購入したり、サービスを受けた人が、売った人に対し、消費税込み、もしくは消費税を後から足した金額を支払い、売り手側は受け取った消費税を税務署に納税する仕組みになっています。
ただし消費税を受け取る売り手側も、仕入れなどで消費税を支払っていますので、その分は差し引いて納税することになります。
また消費税を納税する義務があるのは、売り手側全てではなく、一部の事業者となっています。
消費税はどうやって申告するの?
消費税の申告を行う場合は、納税義務があるかどうかを確認し、課税方式を選ぶ必要があります。
その流れについて、詳しくご紹介します。
1.消費税申告の対象者なのか確認する
課税対象となる対象の年に、売上が1,000万円以上ある場合は対象となりますが、細かな区分がありますので、税理士などに確認が必要です。
2.消費税・税区分の設定を行う
消費税の課税方式を選択し、合わせて消費税込みの経理をするか、税抜きで経理をするかを決めます。
3:適切な税区分で取引を登録する
課税方式と、売上かそれとも仕入れかなど取引の種類に応じて、また税込みが外税かなどによっても変わるので、それぞれの取引を登録します。
なお、1で免税と判定されていても、取引に関する税区分は適切なものを選択します。
4:消費税の集計をチェックする
登録した取引の税区分をチェックし、必要があれば修正します。
5:税務署で消費税の確定申告を行う
申告書に必要事項を記入して作成し、税務署に提出・納税します。
申告期限は、確定申告よりも猶予期間があり、原則として、個人事業主は翌年3月31日まで、法人は期末日の2ヶ月後までとなっています。
6:帳簿に消費税の納付・還付について記入する
申告した消費税の納付・還付について、仕訳として記入及び登録します。
消費税の課税事業者かどうかを確認する
消費税を納税する義務があるかどうかは、売上規模からも判断できますが、単純に売上の金額だけでは判定ができません。
また免税となる場合にも条件がありますので、最終的には税務署や税理士の方に確認してもらいましょう。
課税事業者かどうか、または納税が免除されるかについては、以下のページで確認ができます。
消費税の納税については、開業から2年以内の場合は免除対象ですが、その対象となる期間についてはいくつか条件がありますので、国税庁の以下のページで確認しておきましょう。
課税売上に値引・割戻(リベート)・返品・割引があった時の消費税調整の仕方

課税対象となる資産について、売上を行った後にその売上の値引きなどを行った場合には、消費税の調整が必要となります。
調整が必要となる取引は、以下のものです。
・値引をした
・返品があった
・取引先に対して代金を支払った際に割戻があった
・卸売業者、製造業者などに対して差額を支払った
・支払期日より早く支払いを受け、売上割引を行った
・海上運送事業者が支払う船舶の早出料
・販売促進目的の販売奨励金を使用したことで増加した販売数量や販売高に応じて、取引先に金銭で支払ったもの
・協同組合等から組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の対価となる部分に応じた部分
消費税の調整方法は?
消費税の調整については、通常は課税標準額に対する消費税額から、値引や割戻、返品、などの場合に生じた消費税額を控除します。
ただし、不動産取引など、長期にわたり継続していくものについては、その条件によって、資産の金額から対象となる金額を控除する方法もあります。
消費税の調整はどの期間に行う?
消費税の調整ができるのは、割戻や値引などがあった課税される期間内となります。
割戻や値引の元となる仕入れなどの課税売上があった時には調整はできませんので、年度をまたぐ場合などには注意が必要です。
消費税の調整を行わない場合もある?
消費税は納税する人に不利にならないよう、二重支払いとならないよう調整を行わないこともありますので、以下の場合は注意が必要です。
・免税事業者であった課税期間に行った仕入れなどのやり取りをした後、課税事業者となった課税期間で値引きを行った場合
・課税事業者であった課税期間に行った仕入れなどのやり取りの後、免税事業者となった課税期間で値引きを行った場合
線引きが明確でない場合のリベート
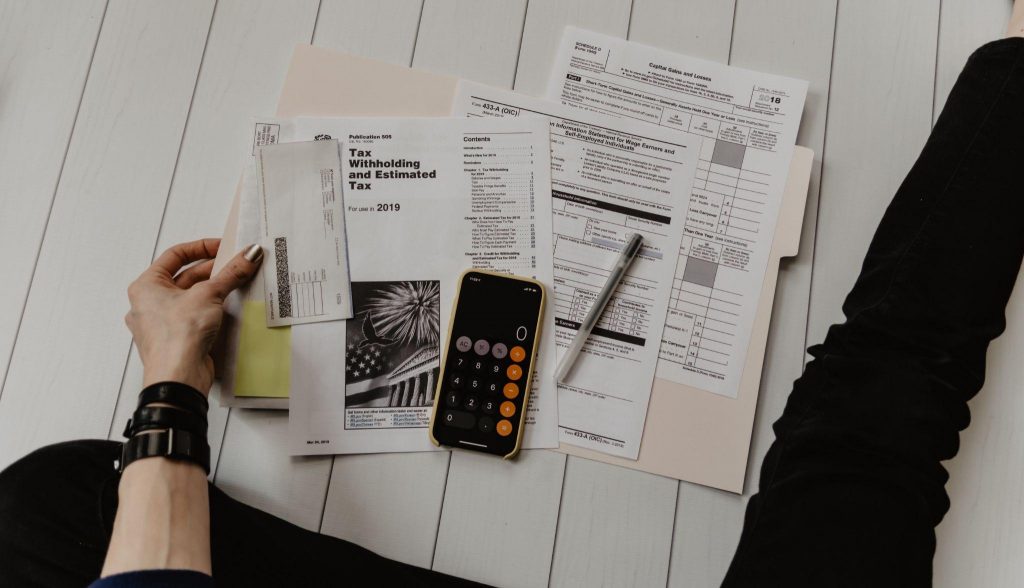
リベートには、原則的なもの以外にもさまざまな形式のリベートが存在します。ここでは、線引きが明確でない場合のリベートについて解説します。
売上に紐づいていないリベート
基本的なリベートは、仕入れた商品の量や決済した金額に応じて支払われますが、売り上げに紐づいていないリベートも存在します。
手数料や交通費、物流コスト、物流センターの使用料など、企業間の取引ではさまざまなリベートの形があります。中には、POP広告費やマネキンにかかる費用などを含めている企業もあり、これらは売上に紐づいていないリベートと呼べるでしょう。
これらのリベートは対価の返還に当てはまっているため、飲食料品に関わる取引の場合は軽減税率の対象となります。ただ、役務の提供に関わる取引の場合は、軽減税率の対象ではなくなります。取引相手と共通の認識を持っておく必要があるため、事前に契約書などに説明を残しておくといいでしょう。
また、個人の頑張りに対する手当としてのリベートの場合は、仕入れ商品数や決済金額にかかわらず、軽減税率の対象外になります。
税率が混在している場合のリベート
飲食料品などの軽減税率の対象になるものと、酒類などの標準税率が対象になるものが混在して取引されることは少なくないです。
軽減税率の導入により、場合によっては計算の仕方を変えなくてはいけません。
その場合、軽減税率と標準税率のそれぞれの適用分を比率配分して計算する必要があるため、事務作業の負担が大きくなります。
そうなれば、何かしらの対策を講じる必要があります。
センターフィーについて
センターフィーは、小売業が卸売業者やメーカーに請求する物流センターの使用料です。基本的には、物流センターを使用した際の対価として支払います。その額が販売した商品の量に伴って計算される場合でも、飲食料品の仕入れや売上の対価の返還には当てはまりません。また、役務の提供の対価とされるため、軽減税率は対象外となります。
値引・割戻(リベート)・割引の仕訳と消費税まとめ

値引や割引は、会計上でもきちんと仕分けが必要です。
消費税を支払う対象者となった場合、この会計上の仕分けが重要となってきますので、対象者、また免除者であっても、きちんと仕訳することが重要です。