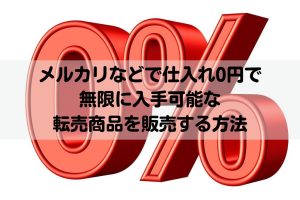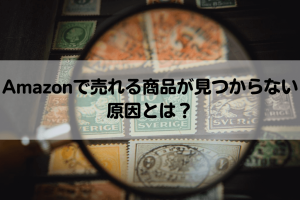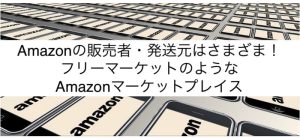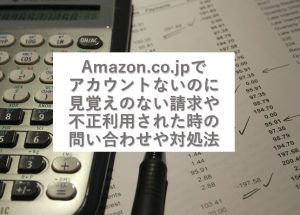宅配便の事業者を比較して、おトクに送れる会社を選ぶ!
ネット通販などの物販ビジネスを始める際には、商品の配送をどうするかは大きな問題です。送る商品の数が増えると、1つ1つの荷物の配送料の少しの違いも、トータルでは大きな違いになります。
ただ、宅配便の料金は、荷物のサイズや重さなどによって細かく分かれているので、単純に比較できない面もあります。また、集荷サービスなどの違いで、使いやすさも変わってきます。
この記事では、国内の主要な宅配事業者5社を比較していますので、配送業者を選ぶ際の参考にしてください。
サービスの違いを把握しよう

宅配便のサービスにも色々あります。会社ごとの違いをチェックする前に、そもそも宅配便にはどんなサービスがあるのかを見ておきます。
配送する荷物の大きさや重さによって利用できるサービスが変わりますし、信書を同封する場合には利用できないといった違いもあります。
宅配便のサービスについて
日本郵便のサービスを例にすると、基本となるサービスは、「ゆうパック」です。縦、横、高さの長さの合計が170cm以下の荷物が送れます。重量は25kgまでです。「重量ゆうパック」というサービスもあり、こちらは30kgまでの荷物が送れます。
送料を安くするためには、「ゆうメール」を使う方法もあります。ただし、重さは1kgまでで、送れる荷物の種類に制限があり、雑誌や書籍、CDやDVDなどが送れます。ただし、信書は同封できませんから、納品書や領収書を同封して送ることができません。
この点、「レターパック」は信書も送れます。重さは4kgまでで、A4サイズまで(340mm×248mm)の荷物が送れます。
「ゆうパケット」は、もっと小さな荷物の配送に適したサービスです。長辺34cm、厚さ3cm以内で、三辺の合計が60cm以内の荷物が送れます。重さは1kg以内です。
安く送るための工夫も必要
このように、荷物を送るサービスにも色々あります。上では日本郵便を例にしましたが、それぞれの宅配事業者でこれに近いサービスを展開しています。どのサービスを利用すれば、コスパよく送ることができるか検討する必要があります。商品によって配送サービスを上手に使い分けて、送料を安く済ませる工夫をするようにしましょう。
また、ゆうパックのような場合は、送る荷物の大きさで料金が変わります。したがって、梱包に使うダンボールを小さくできれば、安く送れます。必要以上に大きなダンボールを使うと、隙間に入れる緩衝材も余分に使うことになってコスト増の原因となりますから、適切な大きさのダンボールを用意することも重要です。
こういった小さな工夫が物販ビジネスで儲けを出すためには必要になるのです。
主要な宅配事業者5社を紹介

ここからは、主要な宅配事業者を5社紹介します。取り上げるのは、ヤマト運輸、日本郵便、佐川急便、西濃運輸、福山通運の5社です。
クロネコヤマトの宅急便でおなじみ「ヤマト運輸」
ヤマト運輸では宅急便と称していますが、ヤマト運輸は宅配便というサービスを最初に始めた会社です。もしヤマト運輸が宅急便のサービスを始めていなければ、今ほど簡単に荷物を送ることはできなかったかもしれないのです。
ヤマト運輸では、60~200サイズまでが「宅急便」で送れます。なお、○○サイズというのは、縦・横・高さの合計の長さが○○cm以内の荷物のことをいいます。
ただし、多くの事業者に共通しますが、サイズごとに上限の重さがあり、それを超えると上のサイズの料金区分になります。例えば、60サイズの上限は2kgなので、箱のサイズが30cm×20cm×10cmであったとしても、重さが3kgの場合は、1つ上の80サイズの料金が発生することになります。
そして、60サイズ未満の荷物は、「宅急便コンパクト」という低料金のサービスが利用できます。宅急便コンパクトは、専用の箱を利用して送ります。
角形A4サイズ以内で、厚さ2.5cm以内、重さ1kg以内の荷物には、郵便受けに配達する「ネコポス」という低料金のサービスもあります。
なお、これからネットショップを開設しようと考えている人は、BASEというネットショップ開設サービスを使うと、「かんたん発送(ヤマト運輸提携)App」というアプリが使えます。荷物の発送が簡単になるので、ネットショップ開設を計画している人は、利用を検討してみてください。
ゆうパックほか各種サービスが充実「日本郵便」

次にご紹介するのは、日本郵便、つまり郵便局の荷物配送サービスです。この記事でもご紹介したように、色々な種類の配送サービスを展開しています。郵便局は小さな町にもありますし、サービスによってはポストへの投函も可能なので、荷物を発送しやすいという利点があります。
郵便局やゆうパック取扱所に荷物を持ち込むと割引になる「持込割引」、1年以内に同一のあて先に荷物を送る場合の「同一あて先割引」、2個以上の同じ種類・あて先の荷物を送る場合の「複数口割引」などの割引制度もあります。
ゆうパックスマホ割アプリを利用することで受けられる割引もあるので、ゆうパックを利用する人は、利用登録を済ませておきましょう。
宅配便サービスではやや後発「佐川急便」

佐川急便は、宅配サービスではやや後発ですが、現在ではかなり充実したサービスを展開しています。
標準的なサービスは、「飛脚宅配便」です。160サイズまで、30kg以内の荷物が送れます。この大きさを越える場合は、260サイズまで、50kg以内の荷物が送れる「飛脚ラージサイズ宅配便」が利用できます。
「飛脚宅配便」に関しては、大きさと重さの上限が決まっていて、どちらかがオーバーすれば、1つ上の料金区分になります。これはヤマト運輸の宅急便と同じ仕組みです。例えば、60サイズなら2kgまでです。
「飛脚ラージサイズ宅配便」の場合は、大きさで料金が決まります。重さは最大50kgの制限があるだけで、料金区分には影響しません。
「飛脚メール便」、「飛脚ゆうメール便」というサービスもあります。飛脚メール便は、三辺合計70cm以内・最長辺40cm以内・厚さ2cm以内・1kgまでの雑誌やカタログなどを配送するサービス。飛脚ゆうメール便は、佐川急便が一旦預かった縦34cm・横25cm・高さ3cm・重量3kg以内の荷物を日本郵便の「ゆうメール」で発送するサービスです。
通信販売事業者向けのカンガルー通販便あり「西濃運輸」

西濃運輸には、「カンガルー特急便」というサービスがありますが、こちらは20kgを越える荷物の配送サービスで、他の会社と同種の宅配便のサービスは「カンガルーミニ便」となります。
カンガルーミニ便では、荷物のサイズをP・S・M・Lの4段階に分けていますが、それぞれ60サイズ、70サイズ、100サイズ、130サイズに当たります。
また西濃運輸には、カンガルー通販便という通信販売事業者向けのサービスがあります。これは商品の箱に直接貼っても剥がしやすい専用の送り状を使ったり、代引きによる配送を行ったりといった通販事業者向けのサービスがパッケージングされたものです。
書籍やカタログなどを配送する際には「カンガルーPostalメール便」というサービスもあります。これは佐川急便の「飛脚ゆうメール便」と同じく、日本郵便のゆうメールを利用したサービスです。
法人相手のサービスが中心「福山通運」

福山通運は、広島県福山市に本社を置く会社です。提供しているサービスは法人向けのものが多いのですが、「フクツー宅配便」のような個人でも利用できるサービスもあります。
フクツー宅配便は、他の事業者と同じく、荷物の大きさと重さで配送料が決まるサービスで、三辺の大きさが合計160cm以下、30kgまでの荷物が送れます。
「フクツーメール便」というサービスもありますが、法人限定となっています。三辺の合計が70cm以内、600g以下の荷物が送れます。
主要5社の宅配便のサイズ規定と料金を比較

ここからは、上記の5つの宅配事業者について、サイズ規定と配送料金を確認していきます。基本的に、日本郵便のゆうパックやヤマト運輸の宅急便といった、その事業者が提供している標準的なサービスを比較に使います。なお、各種割引を使っていない場合の料金です。
ヤマト運輸「宅急便」のサイズ規定・料金
ヤマト運輸の宅急便の場合、サイズは60・80・100・120・140・160の6段階に区分されます。それぞれ重さは、2kgまで・5kgまで・10kgまで・15kgまで・20kgまで・25kgまでとなっています。
料金は、関東から関西まで送った場合で、それぞれ1,060円・1,350円・1,650円・1,970円・2,310円・2,630円です。
参考:宅急便運賃一覧表
以下の各事業者については、このヤマト運輸のサービスを基本にして、多少コメント付しておきます。
日本郵便「ゆうパック」のサイズ規定・料金
日本郵便のゆうパックの場合、サイズ区分は7段階です。60・80・100・120・140・160に加えて、170があります。重さに関しては、一律で25kg以内という制限があるだけですから、制限内ならサイズだけで料金が決まることになります。
料金は、東京から近畿まで送った場合で、それぞれ970円・1,200円・1,440円・1,690円・1,950円・2,160円・2,530円です。
料金はやや安めです。重さに関しては、上限があるだけで一律なので、小さくて重量があるものを送る場合は、日本郵便で送るメリットが大きくなります。
佐川急便「飛脚宅配便」のサイズ規定・料金
佐川急便の飛脚宅配便の場合、サイズ区分は5段階です。60・80・100・140・160で、120がありません。それぞれ重さは、2kgまで・5kgまで・10kgまで・20kgまで・30kgまでとなっています。
料金は、関東から関西まで送った場合で、それぞれ970円・1,280円・1,610円・2,100円・2,340円です。
全体的に安めの設定ですが、120サイズの区分がなく140サイズ扱いになってしまうので、三辺合計120cm程度の荷物を送る場合は、割高になります。30kgまで送れるのはメリットです。
西濃運輸「カンガルーミニ便」のサイズ規定・料金
既に書いたように、西濃運輸の他社の宅配便に近いサービスは、カンガルー特急便ではなくカンガルーミニ便です。サイズ区分はP・S・M・Lの4段階、それぞれ60・70・100・130に相当します。重さは、2kgまで・5kgまで・10kgまで・20kgまでとなっています。
料金は、関東から近畿まで送った場合で、それぞれ1,023円・1,276円・1,529円・1,661円です。
参考:カンガルー宅配便運賃表
料金は多少安めですが、区分が4段階で、20kgの荷物までしか送れないので、使いにくい場合もあるでしょう。なお、20kgを超える荷物はカンガルー特急便で送れます。
福山通運「フクツー宅配便」のサイズ規定・料金
福山通運のフクツー宅配便の場合、サイズは60・80・100・120・140・160の6段階に区分されます。それぞれ重さは、2kgまで・5kgまで・10kgまで・15kgまで・20kgまで・30kgまでとなっています。サイズの区分はヤマト運輸と同一ですが、最大サイズの重さが30kgとなっている点が違います。
料金は、関東から関西まで送った場合で、それぞれ1,120円・1,350円・1,560円・1,810円・2,020円・2,460円です。
参考:フクツー宅配便料金表
少しですが料金が高めです。ただ、最大サイズで30kg近い荷物を送るときには便利です。
宅配便で送れないものをチェック

宅配便は何でも送れるというわけではありません。一般的に送ることができないもの、航空便では送ることができないもの、航空便の場合は事前に申請が必要なものなどがありますから、しっかり確認しておきましょう。
宅配便で送ることができないもの
以下の内容はヤマト運輸の公式ホームページに記載されているものを参考にしています。基本的には、どの宅配事業者も同じような内容になっていますが、実際に荷物を送る際には、自分が利用する事業者のホームページ等を確認するようにしてください。
具体的に送ることができないものとしては、以下のようなものがあります。
まず、現金、小切手などの有価証券類、クレジットカードなどのカード類があります。また、パスポートや受験票などの再発行が困難な書類も送ることができません。原稿やテープ、フィルム類も再現不可能なものに関しては同様です。
ペット類、毒物・劇物、遺骨や位牌、銃砲刀剣なども送れません。花火、灯油など引火性があるもの、他の荷物に損害を及ぼすおそれがある荷物、信書も送ることができません。法令に違反するものも送れません。
なお、一つの梱包の価値が30万円を越えるものは宅急便では送れませんが、ヤマト便でなら送ることができます。
航空機で輸送することができないもの
火薬類、高圧ガス、引火性の液体、可燃性物質などの危険物は航空機で輸送することができません。酸化性物質、毒物類、放射性物質、腐食性物質なども同様です。マニキュアや除光液なども、その他の有害物質として航空機輸送ができないことになっています。
海外に送るといった場合だけでなく、宅急便タイムサービスを使った場合などにも、航空輸送が行われることがあるので、注意してください。
事前申請や梱包方法によっては、航空機輸送ができるもの
そのままでは航空機輸送ができなくても、事前に申請して適切な梱包を行えば、送ることができるものもあります。
ドライアイス、リチウムイオン電池を内蔵した製品、GPSや電波を発信する機器がこれに当たります。これらを送りたい場合は、提出書類や梱包方法を事前に確認するようにしてください。
その他の宅配便に関する情報について

最後に、これまでにご紹介してきたもの以外の情報をまとめて記載しておきます。一部、既に既述した内容を含んでいますが、ご容赦ください。
集荷方法と持参割引について
宅配便の集荷の際には、電話やWebサイトで依頼すると、自宅まで取りにきてくれます。
集荷を依頼せずに、宅配事業者の営業所に直接持ち込むと、100円~200円程度の割引が受けられます。ヤマト運輸や日本郵便の場合、提携しているコンビニへの持ち込みでも割引が適用されます。
なお、配送先を事業者の営業所止めにすると、送料の割引を受けられる場合が多くなっています。配送先に指定できない営業所もあるので、営業所止めを利用する際には、事前に配送先として指定可能かどうか確認してください。
荷物の受け取り方法
荷物の受け取り方法は、自宅での受け取りが基本ですが、他にも色々な手段が用意されています。宅配ボックスでの受け取りや営業所止めは、多くの事業者で可能です。
ヤマト運輸、日本郵便、佐川急便の場合は、提携しているコンビニでも受け取れます。また、ヤマト運輸では、直営店・取扱店のほか、宅配便ロッカーでの受け取りも行っています。
送り状の印刷サービス
送り状は、手書きで作成することもできますが、パソコンやスマホアプリを使って印刷することができるサービスを提供している事業者もあります。
物品販売を行う場合は、送り状の作成にかかる労力・時間はできるだけ削減したいものです。発送作業の効率化のために、こういったサービスは積極的に利用するようにしましょう。
発送した荷物の追跡
発送した荷物の追跡は、各事業者のホームページにある追跡サービスに、送り状の番号を入力することで可能な場合が多くなっています。
事業者によっては、配達完了をメールで知らせてくれるサービスもあるので、これらを利用することで、お客様に確実に商品が届いたことを確認することができます。
配達日、配達時間の指定
基本的にどの事業者も配達日・配達時間の指定が可能となっています。通常は配達日時の指定に別料金は発生しません。
ただし、「翌日の○時まで」といった特に急ぎの配達に関しては、別サービスとなって料金が変わったり、オプション料金が加算されたりします。例えば、ヤマト運輸の場合の「宅急便タイムサービス」、佐川急便の場合の「飛脚ジャストタイム便」といったものです。
まとめ

主要5社を比較しつつ、宅配便のサービスについて紹介してきました。利用する宅配事業者を決める際には、料金はもちろん大事です。各種の割引サービスもありますから、それらも検討した上で、依頼先を決めてください。
ただし、配送する商品によっては、クール便などのオプションサービスの充実度も考慮する必要があります。自分が送る商品に合ったサービスを提供している事業者を利用するようにしてください。