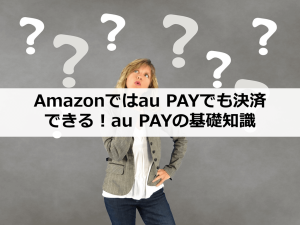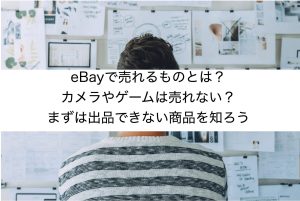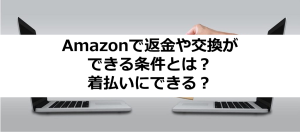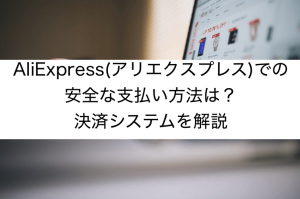「勘定科目がよくわからない」
「送料の勘定科目の仕訳方法がわからない」
「送料を節約したい」
仕入れ業務の際、煩雑な送料回りの計上方法にお困りではないでしょうか?
仕入れる商品数が少ないうちは送料を気にする必要はないかもしれませんが、多くなってくると送料をすべて計算して管理するのは大変ですよね。
しかし、商品の仕入れにかかる経費を把握しておけば、本来得ることができる利益を失わずに済みます。
また、勘定項目の仕組みを理解しておけば、確定申告のときにも役に立ちます。
そこでこの記事では、以下の内容を解説します。
・勘定科目について
・送料の勘定科目の仕訳方法
・送料の節約方法
本記事を参考に送料をできる限り節約して、利益の最大化に努めましょう。
利益計算における勘違いについて

転売の基本は、「商品を安く仕入れて、高値で販売する」ということです。
勘違いしてしまいがちですが、利益は売値から仕入れ値を引いた価格ではありません。
利益とは、売値から仕入れ値+販売手数料+送料を引いた価格のことです。
販売手数料は一定額ではないので、あらかじめ調べておきましょう。
また、上述したとおり、送料についても理解しておかないと、本来得られるべき利益を手に入れ損なうことにもなりかねません。
いかに経費を抑えるかが転売のカギです。
一つずつ順を追って理解していきましょう。
利益を最大化するために送料を把握する必要がある
転売のキモは「経費をいかに減らせるか」にあるので、商品を送るときは可能な限り着払いにしたり、送料は別で支払ってほしいところです。
しかし、買う側にとっては「送料込み」の方がわかりやすいので、こちらを望む傾向にあります。。
なので、送料の計算には注意を払い、利益を最大化するためにどうしたらいいか考えるようにしましょう。
送料は距離、サイズ、重さなどによって変わる費用
送料は送り主の地域と送り先の地域の距離、発送方法、サイズ、重さによって変化します。
例えば、佐川急便の飛脚宅配便で関東地方から荷物を送る場合、同じ関東地方に荷物を送るのと南・北九州に荷物を送るのとでは、料金が約1.5倍違います。
この場合は、関東圏に送るほうが安価です。


また、サイズ60で重さ2㎏のときとサイズ160で重さ30㎏のときでは料金が約2倍以上も違います。
この場合は、サイズが小さく重さが軽いほうが安価です。
他にもメルカリでヤマト運輸のらくらくメルカリ便を利用すれば、送料が全国一律になるので、商品によっては送料を1/2や1/3にしたりすることが可能です。
仕入れ値には送料が含まれていることを意識しよう
送料を気にしない人はいないと思いますが、仕入れ値とは商品代+送料であることは覚えておいてください。
これを理解しておかないと、送料を2重に払ってしまう可能性があります。
基本的な仕入れの流れについて

仕入れを理解するには、企業の経理について理解する必要があります。
勘定科目という言葉はご存知でしょうか。
勘定科目というのは日々の取引を帳簿に記載するときに使う科目のことで、「資産」、「負債」、「純資産」、「費用」、「収益」の5つに分かれます。
帳簿には借方(左側)、貸方(右側)に分けて記載します。
この一連の作業を「仕訳(しわけ)」と呼んでいます。
取引発生→勘定科目を考える→勘定科目が決定したらお金を計算するという流れです。
勘定科目について詳細に知ろう
それでは、勘定科目についてさらに詳しくみていきましょう。
勘定科目のポイントは下記の通りです。
1.取引が資産、負債、純資産、収益、費用の5科目のどれに属すかを決めます。
2.決まった勘定科目を借方に書くか、貸方に書くかで金額の増減が決まります。
3.資産、負債、資本の3科目は貸借対照表に記載し、費用、収益の2科目は損益計算書に記載します。
取引のそれぞれが5科目のどれに対応するかは下記の通りです。
資産:現金や預金、商品など。建物も含まれる。
負債:買掛金、預かり金など
純資産:資本金、引出金など
収益:売上、受取手数料など
費用:商品仕入高、給料手当、荷造発送費、販売促進費など
仕訳の仕方について
具体的に企業が商品を仕入れたときの仕訳の流れは以下のとおりです。
1.商品を仕入れた時、仕入高が増加するのが簿記上の取引です。
2.取引を2つの要素にわけます。
3.仕入高(費用)が増え、現金(資産)が減ります。
4.この取引を借方と貸方にわけるのですが、商品仕入高(費用)が増えた場合は借方に記入し、現金(資産)が減ったときは貸方に記入します。
1回の取引で借方、貸方の両方に分かれるわけではなく、取引の内容によって変動しますが、借方と貸方の合計金額は必ず一致します。
これを貸借平均の原則と呼んでいます。
仕訳のやり方(具体例つき)
先ほど、費用が増えたら借方、資産が減ったら貸方と書きましたが、各勘定科目ごとに借方と貸方の記載方法にはルールがあり、これを仕訳法則と呼んでいます。
具体的には下記の通りです。
| 借 方 | 貸 方 |
|---|---|
| 資産の増加 | 資産の減少 |
| 負債の減少 | 負債の増加 |
| 収益の減少 | 収益の増加 |
| 費用の増加 | 費用の減少 |
事例1
現金200万円で会社を設立した
| 借 方 | 貸 方 |
|---|---|
| 現金 2,000,000円 | 資本金 2,000,000円 |
事例2
会社Aが銀行から50万円借り入れた
| 借 方 | 貸 方 |
|---|---|
| 現金 500,000円 | 借入金 500,000円 |
事例3
会社Aがガス代などの費用を40万払った
| 借 方 | 貸 方 |
|---|---|
| 費用 400,000円 | 現金 400,000円 |
事例4
商品40万円を現金で仕入れた場合
| 借 方 | 貸 方 |
|---|---|
| 商品仕入高 400,000円 | 現金 400,000円 |
事例5
商品40万円を掛で仕入れた場合
| 借 方 | 貸 方 |
|---|---|
| 商品仕入高400,000円 | 買掛金400,000円 |
仕入の流れを具体的にみてみよう

一通り、勘定科目について見てきましたが、「送料」はどの勘定科目に含まれるのでしょうか。
送料といっても仕入れ時にかかる費用や商品発送時にかかる費用など様々です。
仕訳の際の送料の扱い方について説明します。
送料の種類について
「送料」を下記の4つのパターンに分けて説明いたします。
1.商品を販売する場合
商品を発送するときに支払った代金は「荷造運賃」という勘定科目にあたります。
具体的には、メール便や宅配便、運送料金がこれに該当します。
また、商品を梱包するときに必要な資材も「荷造運賃」に該当します。
2.商品や材料を仕入れた場合
商品や材料を仕入れるときにかかった送料や運送費は仕入金額に含まれるので、「商品代+送料」を「仕入高」とします。
3.商品以外のものを送った場合
書類を宅配便で送った場合など、商品以外のものを送ったときは「通信費」とします。
4.商品以外のものを購入した場合
パソコンなどの固定資産を購入したときは「取得価額」に含まれます。
例えば、パソコンの購入、配送、備え付け、試運転までにかかる一連の費用をすべて合算した金額は「取得価額」となります。購入代価だけでなく、付随費用も含めて計算しなければなりません。
宅急便送料の勘定科目
商品の発送に宅急便を利用した際の勘定科目は、「荷造運賃」と「通信費」の2種類に仕訳します。
両者には明確な使い分けが必要で、宅急便で商品を届けたことにより売上が発生した場合は「荷造運賃」、クライアントに書類を送付した場合などで売上が発生しなかった場合は「通信費」と仕訳する決まりです。
つまり、商品を発送する際は「荷造運賃」、商品以外のものを発送する際は「通信費」と仕訳しておけば問題ありません。
仕入に関連する送料が勘定科目の原価に含まれる理由
そもそも、なぜ仕入原価に「送料」を含めなければならないのでしょうか。
それは、法人税法上、取得価額に含めるべき費用として「送料」が規定されているためです。
ちなみに、他に取得価額に含めるべき費用としては下記のものが挙げられます。
1.引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等の購入に要した費用
2.買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用
3.販売所から販売所へ移管するために要した運賃、荷造費等
4.特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用
上記のうち2~4の費用が資産の購入価格のおおむね3%以内である場合は、算入する必要はありません。
海外輸入に関わる送料の取り扱い方法について
ちなみに海外輸入品を取り扱う場合、仕入のときにかかる送料や関税は仕入高に仕訳されます。
ただ、送料は荷造運賃、関税は租税公課といったように、どちらも経費として仕訳してもかまいません。
お歳暮・お中元の送料の勘定科目は接待交際費
接待交際費とは、取引先などに対して贈答や接待をした際にかかる費用のことで、お歳暮やお中元を送った場合にかかる費用も含まれます。
取引先にお歳暮やお中元を郵送する時にかかる送料の処理は、贈答品と同じ扱いで接待交際費としての処理です。
仮にお中元が10,000円、送料が1,000円である場合には、全額に当たる11,000円を接待交通費として処理します。
消耗品や固定資産の送料に関わる勘定科目
消耗品を購入した際に発生する送料は、勘定科目の消耗品費に含めることができます。
消耗品費とは取得価額10万円未満、使用可能期限が1年未満の消耗性のあるものを購入した際に仕訳する費用です。
送料を分けて計算したい場合は、荷造運賃として仕訳することも可能ですが、荷造運賃は商品を発送した際に使用する勘定科目なので基本的には消耗品費に含めましょう。
また、固定資産を購入した際の送料も注意が必要です。
固定資産を購入した際に発生した送料は、原則固定資産の取得価額に含めるよう決められています。
運送保険料や購入手数料など、付随費用と呼ばれる費用についても送料と同様の扱いにできるため、消耗品や固定資産を購入した時に掛かった費用は全てまとめて計上するのが一番簡単な方法となります。
引取運賃、発送費などの送料の勘定科目について

仕入れのときの送料と顧客に商品を送るときの送料についてより具体的に説明します。
借方と貸方で金額が一致する必要があるのは変わりませんが、仕訳の流れが異なりますので、しっかりと理解しておきましょう。
商品購入した際の送料の勘定科目について
仮に取引先から商品を引き取ったときにかかる引取運賃について、どちらが負担するべきなのでしょうか。
実情は取引先とのパワーバランスで決定されることが多いですが、一般的には「引取運賃」という独立した勘定科目を設けずに「仕入金額」に含めます。
例をみてみましょう。
96,000円相当の商品を仕入れ、代金は掛けとし、引取運賃4,000円は現金で支払った場合です。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 仕入 100,000 | 買掛金 96,000 |
| 現金 4,000 |
仕入の方に仕入れ代金と引き取り運賃の合算価格が記載されているのがお分かりいただけるでしょうか。
発送費の負担について
当然のことですが、顧客に商品を送る際にも送料はかかり、全国へ商品を送っている会社の場合などは送料が大きな問題になってきます。
この送料を自社負担にするのか、顧客負担にするのかで仕訳の仕方が変わるので、例を使ってそれぞれのケースを見ていきましょう。
500,000円相当の商品を売り上げ、代金は掛けとし、送料5,000円は現金で支払った場合。
1.送料を自社で負担する場合
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 売掛金 500,000 | 売上 500,000 |
| 発送費 5,000 | 現金 5,000 |
2.送料を顧客が負担する場合
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 売掛金 500,000 | 売上 500,000 |
| 立替金 5,000 | 現金 5,000 |
最終的に顧客が送料を負担しますが、最初は立替金として仕訳をしておきます。
ちなみに立替金の支払いをしてもらったあとの処理は下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金 505,000 | 売掛金 500,000 |
| 立替金 5,000 |
着払いの場合の仕訳について
仮に仕入れた商品を着払いで受け取ったとして、そのときの仕訳はどうなるのでしょうか。
着払い料金については受け取る側の費用負担になるので、通信費や運送費として仕訳をしていきます。
仕入にかかる費用はすべて仕入として仕訳する必要があります。
なので、商品の仕入れをしたときの着払い料金については仕入として仕訳する必要があります。
たとえば、宅急便の着払い代金3,000円を現金で支払った場合は以下のとおりです。
| 借方 | 賃方 |
|---|---|
| 運送費 3,000 | 現金 3,000 |
通販利用時の送料の勘定科目について
通販を利用した際の送料の勘定科目については「立替金を利用する方法」と「売上に含める方法」の2種類がありますが、どちらの方法をとっても問題ありません。
しかし、今月は立替金を利用し、来月は売上に含めるといった、2種類の方法を混在させるのはやめましょう。
必ずどちらかの方法に統一する必要がありますが、基本的には処理に手間取らない「売上に含める方法」が広く採用されています。
デメリットとして売上が見た目上多くなるため、正確な売上把握をしたい場合は計算の手間と比較して自分のビジネスに合った方法を選択しましょう。
送料はなぜ取得原価に含めなければいけないのか

すでにご説明した通り、商品を仕入れたときの送料は取得原価に含まれますが、これには明確な理由があります。
細かいことかもしれませんが、大切なことなので説明しておきます。
取得原価に送料を含めないで計算すると問題になる理由
商品を仕入れた時、送料を取得原価に含めない場合と含めた場合について具体的な数値を用いて説明いたします。
【前提条件】
当期、1個5,000円の商品を50個仕入れました。
その時の送料が13,000円だとします。
そして、この商品を1個10,000円で販売するとします。
当期中に25個、翌期には残りの25個が売れました。
*期首に商品在庫がないものとします。
・送料を取得原価に入れないで運送費とした場合
当期の売上:10,000円 × 25個 = 250,000円
当期の費用:売上原価が5,000円 × 25個 = 125,000円、運送費が13,000円なので、合計の138,000円
当期の利益:収益250,000円 – 138,000円 = 112,000円
翌期の売上:10,000円 × 25個 = 250,000円
翌期の費用:売上原価が5,000円 × 25個 = 125,000円
翌期の利益:収益250,000円 – 費用125,000円 = 125,000円
当期と翌期で利益が異なるのはおかしいですよね。
・送料を取得原価に含んだ場合
当期の売上:10,000円 × 25個 = 250,000円
当期の費用:5,000円 × 50個 + 送料13,000円 = 263,000円で売上原価は5,260円/個なので、5,260円 x 25個 = 131,500円
当期の利益:収益250,000円 – 費用131,500円 = 118,500円
翌期の売上:10,000円 × 25個 = 250,000円
翌期の費用:5,260円 × 25個 = 131,500円
翌期の利益:収益250,000円 – 131,500円 = 118,500円
このように、送料を取得原価に含めると利益も同じになります。
正しい期間損益計算について
なぜ、送料として取得原価に含めずに別建てで計算すると正しい期間損益計算ができないのかというと、「費用収益対応の原則」に沿っていないからです。
費用は実際に生じた利益に対応した金額しか計上できないのです。
上記の例でいうと、当期に25個しか売れていないので、送料も25個分しか計上してはいけないのです。
つまり、送料は商品を仕入れたときの代金とセットで考えなければいけないということです。
送料を別建てで計算してしまった場合
運送費を間違えて別建てで計算してしまう可能性もあります。
今回の場合、運送費13,000円を売上原価(125,000円)と期末商品(125,000円)に6,500円ずつ配分して、期末商品に配分した送料については翌期に繰り延べをすればいいのです。
送料のうち、6,500円を繰り延べるために資産に振り替えて、翌期に再振分仕訳をすれば問題ありません。
ただ、会計処理としては正しくない方法なので、ご注意ください。
送料を見直して、利益を増やす
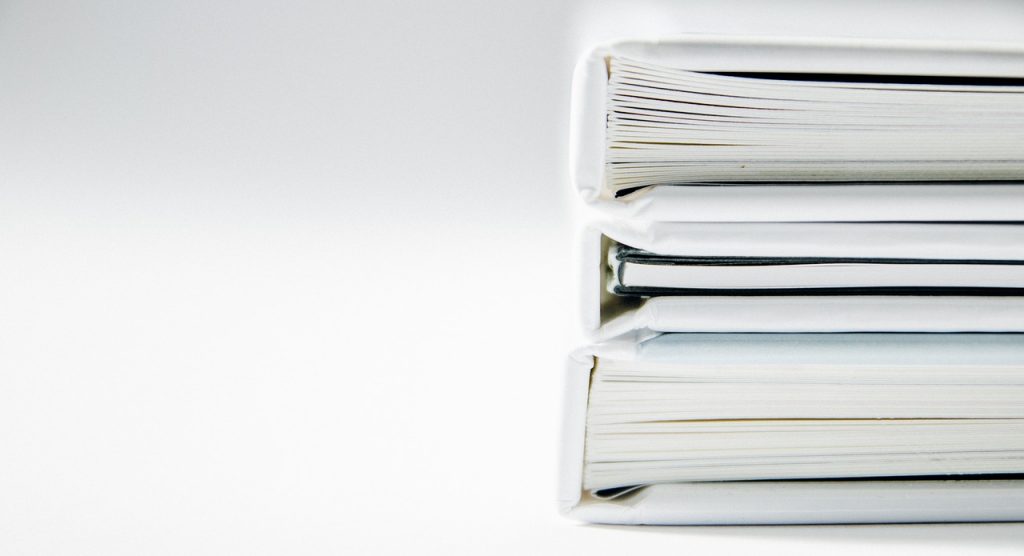
「安価で仕入れて、高値で販売する」のが商売の基本なので、原価をいかに抑えるかということに注力する人は多いですが、送料を抑えるという発想をしている人はなかなかいません。
利益を増やすには、原価を抑えるだけでなく送料を抑えることも大事です。
優先すべきことは安く仕入れることですが、送料にも気をつけましょう。
販売量が多くなってきた時は、なおさら送料に注意しましょう。
お店で商品を購入した時の送料について
思っていた以上に多く仕入れてしまった場合は購入したお店に頼んで、郵送してもらうという手があります。
お店によっては一括送料~円という条件で郵送をしてくれるところもありますし、そういうお店に他店舗で仕入れた商品も同梱してもらえれば送料が抑えられます。
どうやって仕入れているか調べて改善していこう
一括郵送で送料を節約する以外にも、生産者から直接仕入れたり、現金問屋を活用したり、仕入時期や仕入条件などの項目を調べるなどして、さらに節約することができないか検討するようにしましょう。
ヤフオクの場合の送料節約法について
ヤフオクの場合、送料は落札者または出品者が負担します。どちらが負担するかは、出品者が出品する際に決められます。
送料が落札者負担の場合は、同じ出品者から複数購買し同梱発送してもらえれば、送料負担を軽減することができます。
まとめ
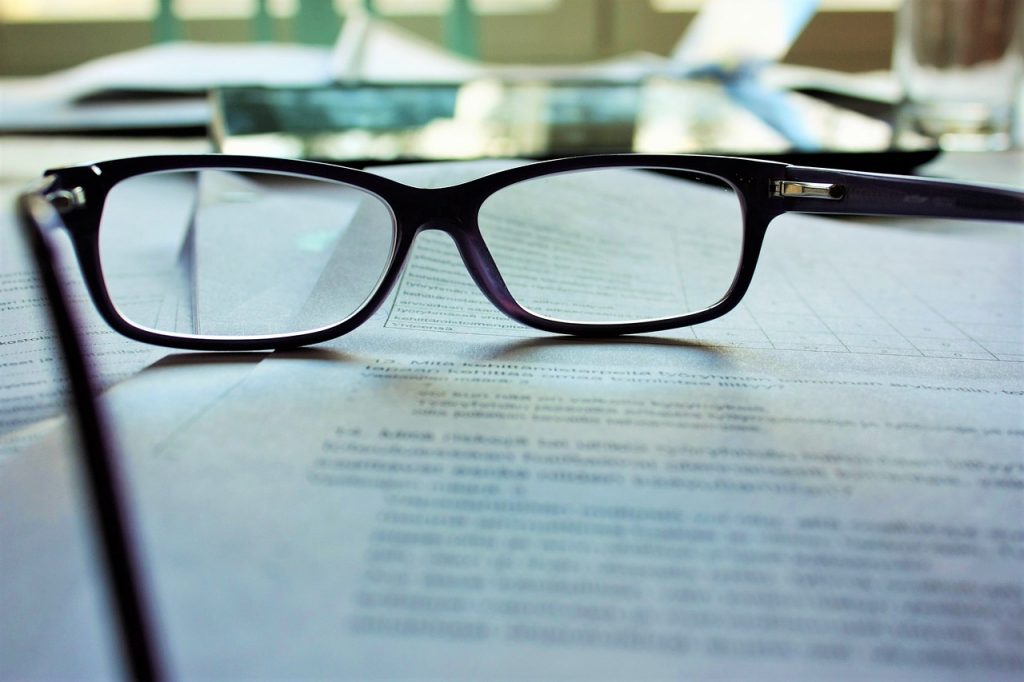
仕入の時の送料は0にはできませんが、節約する方法はいくつかあります。
取引のパターンごとに最安値を選択していきましょう。
商売のコツは安く仕入れることにありますが、コスト削減という観点から送料についてもしっかり考慮するようにしましょう。