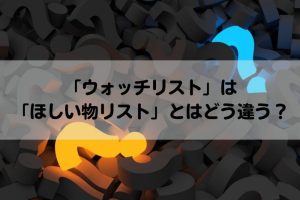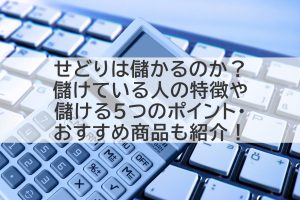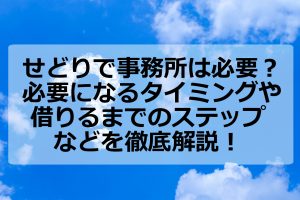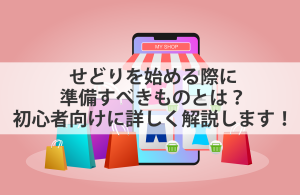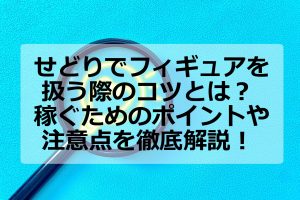初心者必見!Webサイトを立ち上げる方法を分かりやすくご紹介
多くの人がスマホやインターネットを利用する昨今、「自分もWebサイトを立ち上げれば、収入を得られるかなぁ」と考えている方は少なくないでしょう。自分のWebサイトを持っていれば、ネットショップの集客に活用できるだけでなく、広告を表示させればWebサイト自体から収入を得ることもできます。
しかし、どうすればネット上にWebサイトやブログを作れるのか、その具体的な方法について悩まれている方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、初心者向けにWebサイトの立ち上げ方を解説します。Webサイトの構築に興味のある方は、ぜひご覧ください。
Webサイトを立ち上げる前に知っておくべき基礎知識
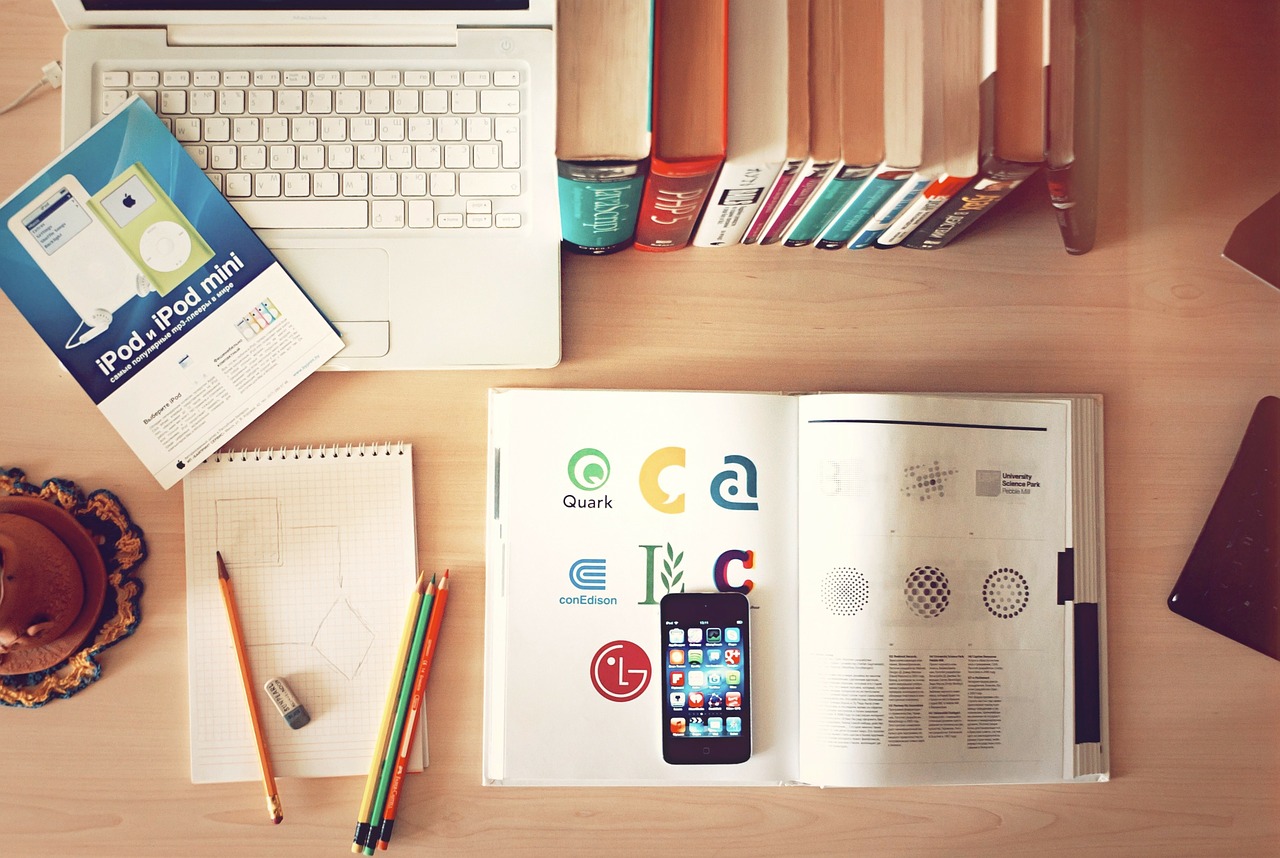
「善は急げ!」ということで、できるだけ早く作成に取り掛かりたいと思うかもしれません。しかし、最低限の知識は身につけておいたほうが以降の作業がグンと楽になります。
そこでまずは、Webサイトやブログを立ち上げるにあたり、知っておくべき基礎知識を解説しようと思います。
Webサイトを見てもらうにはサーバーが必要
ご存知の通り、Webサイトは世界中に公開されます。日本のWebサイトだから日本国内の人限定というわけではなく、言語の通じない海外の人も見ることができます。でも、どうしてどこかの誰かが作ったWebサイトを世界中の人が見ることができるのでしょうか。
それは、Webサイトが「サーバー」という世界中からアクセスできる場所に置かれているからです。サーバーにあるWebサイトへは、特別なロックがかかっていない限り、世界中からアクセスできるのです。
つまり、作成したWebサイトをみんなに見てもらうには、「サーバー」が必須ということです。
レンタルサーバーには有料のものと無料のものがある
「じゃあ、サーバーはどうやって用意すればいいの?」となりますが、サーバーは簡単にレンタルできます。その手続きも簡単そのもの。
サーバーの中には、無料でレンタルできるものあります。「無料だからラッキー」と思ってしまうかもしれませんが、注意も必要です。なぜなら、無料でレンタルできるサーバーを利用すると、あなたが立ち上げたWebサイト上に「広告」が表示される場合があるからです。
自分好みのWebサイトをデザインして立ち上げたのに、好みではない広告を勝手に貼られるのは嫌ですよね。そのようなときは、有料のサーバーをレンタルしましょう。有料といっても月1,000円程度からレンタルできますし、それに有料のサーバーなら、「独自ドメイン」という自分だけのWeb上の住所も取得できます。
Web上の住所となるドメイン
ドメインというのは、Web上の住所のこと。例えば、「http://www.yahoo.co.jp」の中の「yahoo.co.jp」の部分がドメインです。独自ドメインなら自分の好きなアルファベットを設定することも可能。ドメインを含んだWebサイトのアドレスを友人や知り合いに公開すれば、みんなに自分の立ち上げたWebサイトを見てもらえることでしょう。
特にWebサイトをビジネスで利用する場合は、独自ドメインを含んだアドレスの方が信頼されるのでぜひ取得しておきましょう。
無料レンタルサーバー・有料レンタルサーバー、それぞれのメリットとデメリット
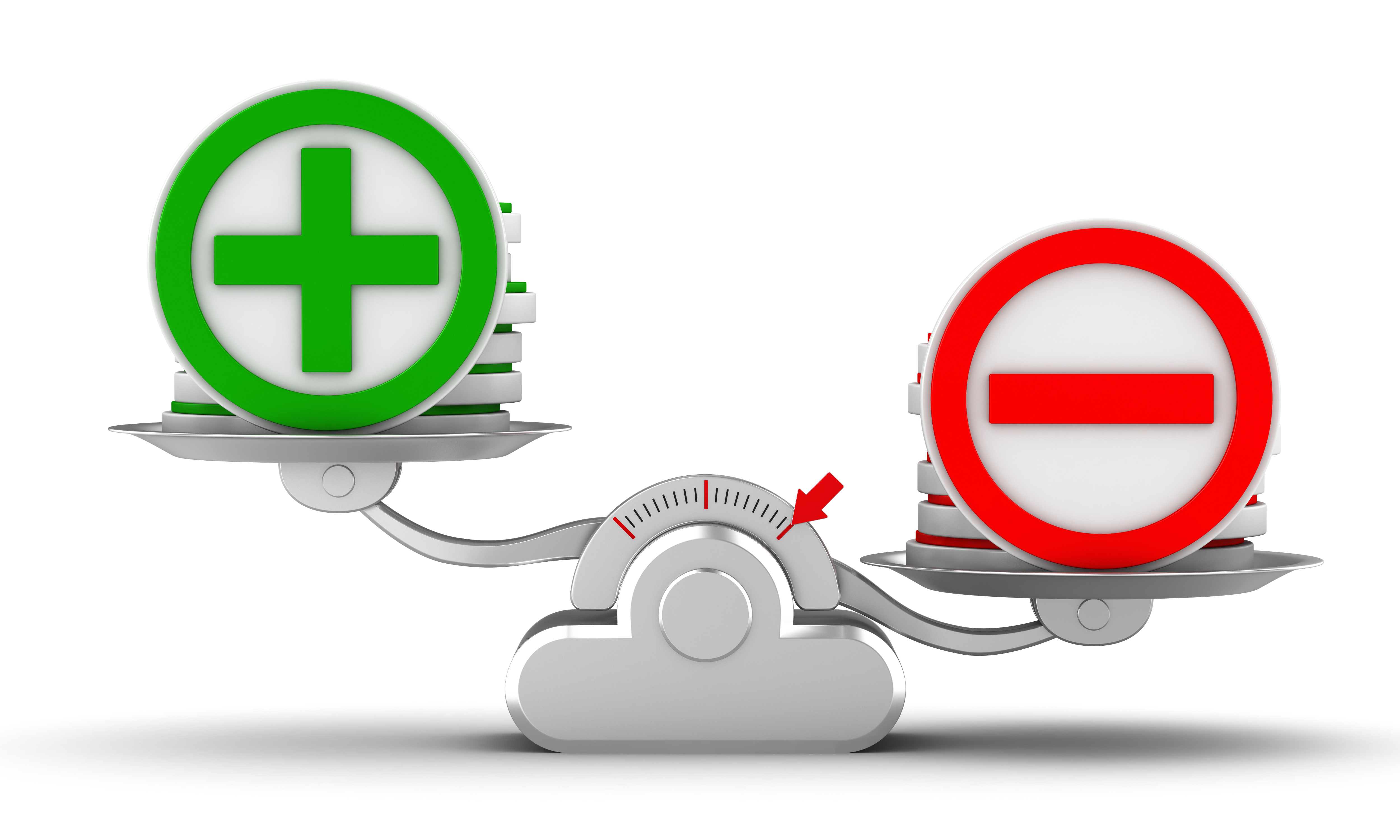
先ほど、レンタルサーバーには無料のものと有料のものがあるとお話しました。どちらを利用しようか悩んでいる方のために、ここからは、無料レンタルサーバーと有料レンタルサーバー、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
無料レンタルサーバーのメリット・デメリット
無料レンタルサーバーは、なんと言っても無料で利用できるのが最大のメリットです。そのため、「低リスクでとりあえずWebサイトを立ち上げてみたい!」と考えている人におすすめです。
しかも、ドメインはサーバーが用意してくれます。そのようなドメインは最初から「ドメインパワー」が強いので、Google検索でも上位表示されやすくなります。
しかしながら、先ほどもお話した通り、自分のWebサイトの中に広告が表示されたり、突然サービスを終了されてしまう恐れがあったりといったデメリットも存在します。
有料レンタルサーバーのメリット・デメリット
有料サーバーのデメリットと言えば、なんと言ってもお金がかかってしまうこと(当たり前ですが…)。しかし、お金がかかるといっても初期費用3,000円、月額料金1,000円程度のレンタルサーバーも多くあります。毎月コーヒー3杯分程度の値段で色々なメリットを享受できるのですから、そこまで大きなデメリットとは言えないでしょう。
有料サーバーのメリットとしては、自分だけの独自ドメインが利用できるのが大きいですね。他にも、無料のレンタルサーバーよりもWebサイトの表示速度が速かったり、自分のドメインを使ったメールアドレスを取得できたりと、サービスが充実しているところが「さすが有料!」といったところです。
Webサイトの立ち上げにあたって覚えておくべきこと

利用するサーバーに目星が付いたら、次はWebサイトの設計です。ただ、その前にWebサイトを立ち上げるにあたって覚えておくべき知識がありますので、ここでご紹介しておきます。
コンテンツを充実させる
Webサイトを制作するにあたっては、どんなWebサイトにするかを考えなければ何も始まりません。
とはいえ、「こんなWebサイトがいいかなぁ、いや、あんなWebサイトの方がいいかも?」などと悩んでしまうと、今度はサイト作りが始まらなくなってしまいます。そこで、自分の作りたいWebサイトのイメージがハッキリしていなくても、まずは無料のレンタルサーバーを利用して、とにかく思いついたコンテンツを作ってみましょう。
趣味程度にコツコツと内容を充実させていくうちに、自分の好きなジャンルや得意分野もはっきりしてくるでしょう。ますは、Webサイトの制作に慣れてしまうことです。本格的なWebサイトの構築はそれからで十分です。
ターゲットを絞り込んでいこう
そうは言っても、思いついたコンテンツを思いついたままに作り続けてしまうと、ごちゃごちゃしたWebサイトになること間違いなしです。例えば、「司法書士資格取得への挑戦!」「大好きなチョコレート」「おすすめのスキンケア」なんていうコンテンツが同一のサイト上に並んでいたら、もう訳が分からないですよね。
Webサイトは、ごちゃごちゃした中にも何らかの統一感が必要です。上記の例であれば、「司法書士を目指している30代女性」をターゲットに、「資格取得」に関する内容に「勉強の息抜きにおすすめのチョコレート」を加え、さらに「勉強で緊張した心を落ち着かせるためのスキンケア」を追加するなど、ターゲットをある程度絞り込んでコンテンツを作成していくのがコツです。
あるテーマを深掘りしていこう
Webサイトのテーマが決まっているのなら、そのテーマを深堀りしていくのがおすすめです。
例えば、先ほどの「司法書士資格取得への挑戦!」がテーマなら、「司法書士になるには?」という基礎知識から始め、それから「おすすめの勉強法」といった実際に資格を目指している人にしか分からない情報を盛り込んでいくようにすると、充実したWebサイトになっていきます。
さらに、テーマを絞り込むことで、次はどんなコンテンツや記事を盛り込んでいけばよいか、自分でもイメージしやすくなるというメリットもあります。
キーワードを考えよう
Webサイトをせっかく立ち上げたんですから、できるだけ多くの人に見てもらいたいですよね。それでは、多くの人にWebサイトへアクセスしてもらうには、どうすればよいのでしょう?
答えは簡単です。Google検索で上位表示されれば良いのです。そうすれば、あなたのWebサイトへのアクセスが増加します。
そのためには、上位表示されやすいコンテンツや記事を増やしていく必要があります。
Google検索を利用するユーザーは、何か調べたいことがあって検索を利用します。例えば、司法書士資格取得を目指すユーザーなら、「司法書士 試験 いつ」というキーワードで検索する人もいるはずです。そこで、「司法書士 試験 いつ」というキーワードに関する記事を書いておけば、そのキーワードで上位表示される可能性が高まります。
他のキーワードに関しても同様です。自分のWebサイトへ訪れて欲しいユーザーがどのようなキーワードを使って検索するかを想定して、Webサイトに加えるべきコンテンツを考えていきましょう。
魅力的なWebサイトを立ち上げるために必要なこと
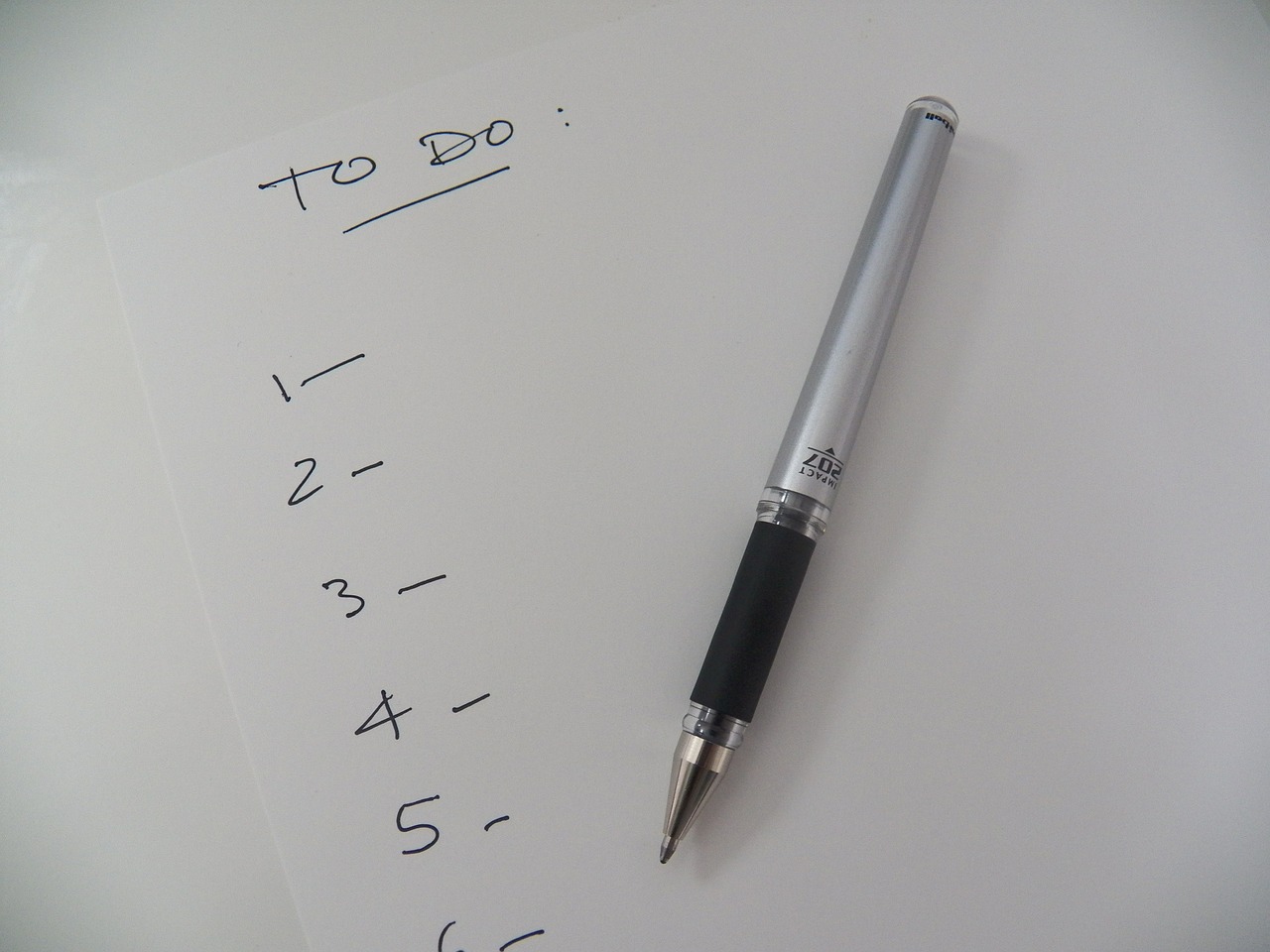
あなたが自分のWebサイトで商品やサービスの販売を開始したとしてもすでにライバルが多くいると、立ち上げたばかりのあなたのサイトは見向きもされない恐れがあります。
ライバルに勝つには自分のサイトを魅力的なものにする必要があります。早速、その方法を見ていきましょう。
ユーザーが求めている商品やサービスをヒアリング
一番簡単な方法は、ユーザーに会い、直接お話を伺うことです。ユーザーといっても、いきなり赤の他人と会う必要はありません。
友人や知り合いとお茶しながら、「どんな商品やサービスがあれば嬉しいか、どんなWebサイトなら安心して購入できるか」などをヒアリングすればよいのです。どのようなWebサイトが魅力的かという話題を通して自分が知らなかったトレンドやブームに関する情報も入ってくるでしょうから一石二鳥です。
魅力的なWebサイトを積極的に利用する
普段からいろんなWebサイトを利用しておくことも重要です。自分が通販サイトを利用したことがないと、自分の通販サイトを利用してくれるユーザーの気持ちが分かりません。
Amazonでも楽天市場でも何でも良いので、積極的に通販サイトを利用して、どんなWebサイトが魅力的なのか常にチェックしておきましょう。
個人でWebサイトを立ち上げる場合は、個人利用者も多い「BASE」や「カラーミーショップ」などのネットショップ作成サービスを利用して立ち上げたWebサイトを見ておくのも参考になりますよ。
他のWebサイトの悪い点をチェックする
利用しやすいWebサイトでないと、ユーザーは商品やサービスを購入してくれません。例え魅力的な商品やサービスがあっても、どのように購入すればよいのかが分からなければ、すぐに離脱してしまいます。
しかし、Webサイトを作成している本人では、自分のWebサイトのどこが悪いのか分かりにくいものです。
そこで、ライバルサイトのチェックです。他の通販サイトを利用していると「この通販サイト不便だなぁ」と感じることはありませんか? その「不便さ」や「不満」は、全てメモに残しておきましょう。ライバルサイトを反面教師とすることで、ユーザーがより利用しやすいWebサイトを作り上げていけるはずです。
Webサイトを立ち上げるコツ

では、いよいよWebサイトを立ち上げる準備をしていきます。先ほどお話した通り、Webサイトを立ち上げるには「サーバー」と「ドメイン」が必要です。一つ一つ、準備していきましょう。
自分に合ったサーバーを選ぼう
一口にサーバーといっても、容量や価格は様々。
Web系のスキルはないけれどWebサイトは立ち上げたいという場合は、「WordPress」が簡単にインストールできるサーバーを選ぶのがおすすめです「Wordpress」を利用すれば、Webデザインやプログラミングのスキルがなくても簡単に本格的なWebサイトが制作できます。
簡単に、ブログや本格的なWebサイトを立ち上げたい方は、「Wordpress簡単インストール対応」と記載されているサーバーを選びましょう。
Webサイトに合ったドメインを選ぼう
ドメインを取得できるサービスも複数あり、ドメインの種類も様々です。ドメインとして有名なのは「.com」ですよね。しかし、「.com」はすでに取得している人が多いドメインなので、希望する名前はすでに取得済みになってしまっている可能性があります。
そんな時は、他のドメインを狙いましょう。「.net」や「.info」など、ドメインの種類は年々増えています。最初の1年は年間100円程度で取得できるドメインも多いので、お気に入りを探してみてください。
また、ドメインに含む単語は、自分のWebサイトに関連するものを選びましょう。例えば、コーヒーを取り扱うWebサイトなら「coffee」、花に関連したWebサイトなら「flower」という単語を加えることで、それ専門のWebサイトだと認知してもらいやすくなります。
コンテンツを充実させていこう
Webサイトで何より重要なのはコンテンツです。記事と画像で構成されたブログのようなWebサイトなら、WordやGoogleドキュメントに下書きしてからWordpressに入力していきましょう。
文字に関しては、Wordpress上でフォントやサイズなどを微調整できます。画像についてはWordpressにアップロードする前に色味やサイズを調整しておくとWordpressにアップロードしてからの作業が楽になりますよ。
また、自身でHTMLやCSSを用いてWebサイトを立ち上げる場合は、Webページを作成してからサーバーにファイル転送を行いアップロードしましょう。ファイル転送ソフトは、契約しているサーバーが提供している場合が多いので、そちらを利用するのがおすすめです。
個人ブログ・サイトの作り方は、下記の記事も参考にしてみてください。充実したコンテンツの作り方まで解説されています。
参考:ブログの始め方を完全攻略!初心者が稼ぐまでの手順7つをプロが解説!
素敵なWebサイトを立ち上げよう!
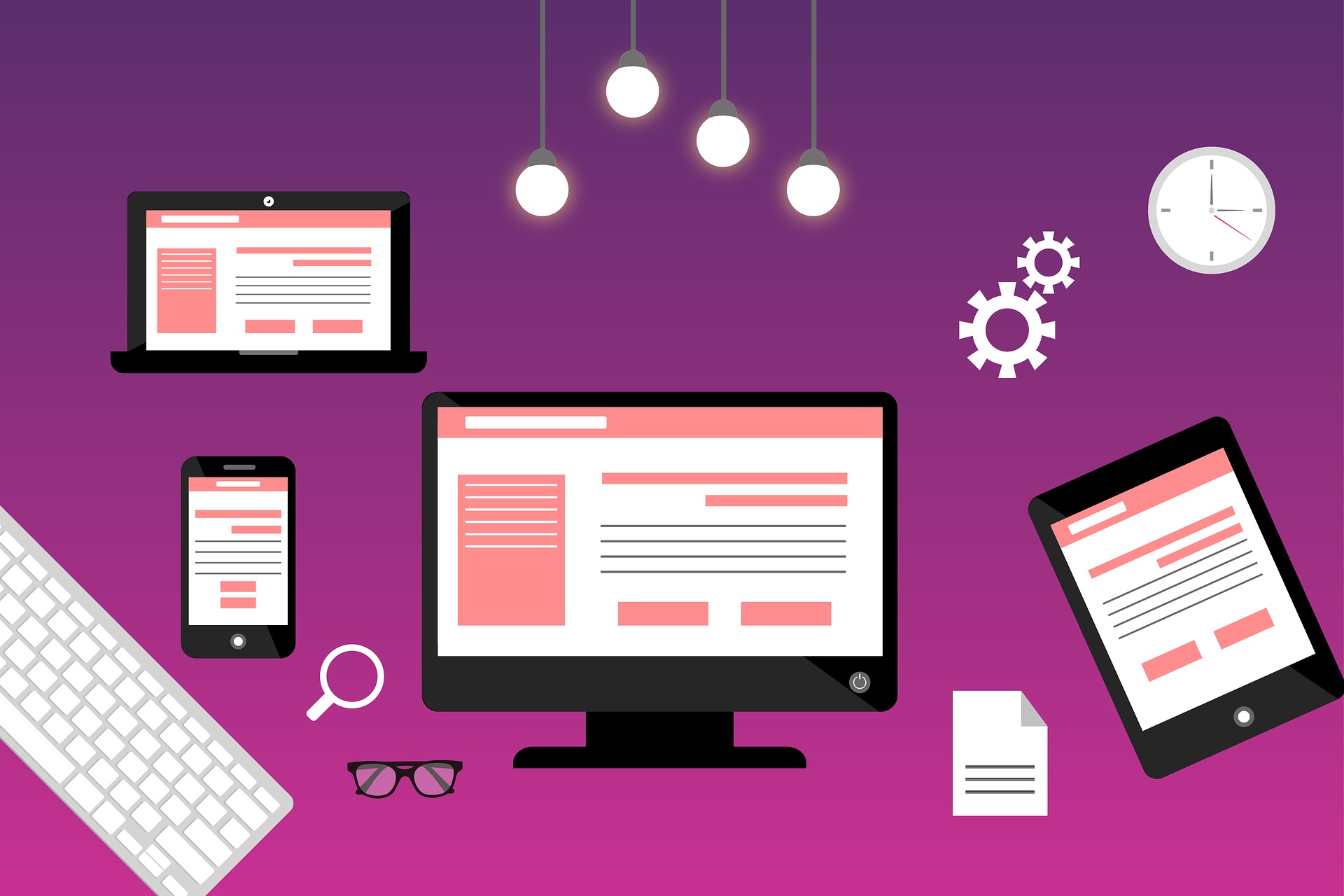
Webサイトを立ち上げれば、ネットショップをオープンさせたり、自分のブログをアップしたりと、いろいろなことができるようになります。しかも、自分のWebサイトを世界中の人に見てもらえるのですから、こんなに嬉しいことはないでしょう。
ぜひ、こちらの記事を参考にして素敵なWebサイトを立ち上げてみてくださいね。