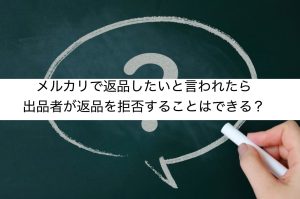日本の独占禁止法(競争法)では、流通を請け負う卸業者や小売業者などに対してメーカーである販売者が販売価格を拘束する行為(再販売価格拘束)を禁止しています。
小売業者などに対してメーカーが「高く売る」ことを禁止するのが「最高再販売価格拘束」で、「安く売る」ことを禁止するのが「最低再販売価格拘束」です。日本では再販売価格拘束が禁止されていますが、具体的に「最高」「最低」どちら(もしくは両方?)を拘束すると違法になるのか、司法による明確な判断はまだなされていません。
海外にも再販売価格維持行為を規制する法律があります。例えば米国では「最低価格」に対する拘束行為を違法とみなし、「最高価格」については寛容な傾向にあります。
この記事では、再販売価格維持行為に対して、国内と海外でどのように判断されているか見ていきます。
「流通・取引慣行ガイドライン」の概要を紹介

再販売価格維持行為に当たるかどうかの指標となるのが「流通・取引慣行ガイドライン」です。
企業に問われるコンプライアンス意識
独占禁止法に違反していると判断された場合、課徴金命令などの経済的制裁を受けるだけでなく、コンプライアンス意識の欠如というレッテルを貼られることになります。そうなると、社会的信用を失うことにもつながります。独占禁止法違反を対岸の火と見るのではなく、高い関心を持つことが重要です。
ただ、独占禁止法の条文は分かりにくいという声が多いのも事実です。個々の企業活動の実態に当てはめて理解することが難しいからです。
「流通・取引慣行ガイドライン」の活用
自社の活動が独占禁止法に抵触するか否かを判断する際に参考になるのが、公正取引委員会が定めているガイドラインです。とくに「流通・取引慣行ガイドライン(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針)」は、独占禁止法に沿った企業活動を行うための考え方や、違法となる具体的な事例を紹介しています。
「流通・取引慣行ガイドライン」に掲載されている内容は、大きく分けると以下のようになっています。
・取引先事業者の事業活動に対する制限
・取引先の選択
・総代理店
再販売価格維持行為について

冒頭でも述べた通り、独占禁止法は、流通業者が販売価格を自由に決定するのをメーカーが妨げることを違法としています。こうした行為は「再販売価格維持行為」と呼ばれ、メーカーがこのような行為を行った場合は罰則の対象になります。
再販売価格維持行為が違法とされる理由は、このような行為を容認すると市場における価格競争が不当に妨げられてしまうためです(独禁法2条9項4号に記載)。価格競争が起こらなければ、消費者はその商品を高い値段で買わざるを得なくなってしまいます。
「最低」再販売価格拘束について
ネット通販市場では商品の流通方法が大きく2通りに分かれています。
・メーカーが直接消費者へ販売する(ダイレクトマーケティング)
・メーカーが卸売業者や小売店に流通を任せる(従来の流通スタイル)
前者の方法であれば消費者に対してブランド価格を打ち出すことが可能ですが、後者の場合は、メーカーの希望とは裏腹に小売業者により安売りをされる恐れがあります。
そのような事態を防ぐためには、メーカーから小売業者などへ拘束力のある「口出し」をする必要が生じます。しかし、これこそが「再販売価格拘束」であり、実際に行ってしまうと違法行為となります。
事例として多いのが「最低」再販売価格拘束です。これはメーカーが小売業者に対し、想定する価格よりも安く商品が販売されるのを禁止するために行う「口出し」です。
仮に、メーカーが安く売りたいと思っている小売業者への出荷を停止したり、出荷数を減少させたりすると、メーカーの都合に合わせた販売戦略が採られることとなり、結果として消費者の選択の余地を奪うことになります。
公正取引委員会は、こうした「再販売価格拘束」に当たる行為に対して規制を定めることにより、消費者にとってメリットのある取引が実現するようルール作りを行っているのです。
日本の場合
ここからは、国内と海外の「再販売価格拘束」に関する規制の違いを見ていきましょう。
まずは、日本。
公正取引委員会は、「正当な理由がない限り」と一言添えた上で、再販売価格拘束は違法としています。
「正当な理由」に当たる場合とは、再販売価格拘束と認められる行為が消費者にとってメリットがあると判断される場合のことです。
実際は、この例外要件に該当するケースはほとんどないため、メーカー企業としては再販売価格拘束に該当する行為を行わないよう注意する必要があります。
米国の場合
米国では、「最低価格」を拘束する行為を違法とする考え方が100年近くに渡り続いてきました。しかし、近年では、個々の事案を考慮し、合理的に判断すべきという司法判断がされたことで、一部では緩和されるようになりました。
欧州の場合
欧州でも、日本や米国と同じように、「最低価格」を拘束する行為を原則的に規制対象としています。ただし、例外として認められる事例がいくつかあります。
例えば、新製品の販売価格やフリーライド(ブランドのタダ乗り)を防止する場合などに「最低」再販売価格拘束を適法としています。
日本でもこうした事例では認めるべきか否か議論を深める必要があるでしょう。
「最高」再販売価格拘束について
「最低」再販売価格拘束の逆が「最高」再販売価格拘束です。つまり、メーカーから流通業者に対してメーカーが希望する価格以上で対象製品を販売することを妨げる行為です。
「最高」再販売価格拘束は商品の高額化を防ぐことに繋がるため、消費者にとってデメリットはありません。
米国の場合
米国では、1997年に連邦最高裁判決において「最高」再販売価格拘束に合理性がある場合は違法とすべきではないと判断されて以来、最高再販売価格拘束の違法性が問題になることはほとんどありません。
欧州の場合
欧州でも、米国と同じように、「最高価格」を拘束する行為を違法とした司法判断は出されていません。ただし、個々の事案を考慮し、消費者に対してデメリットがある取引と認められた場合には違法と認定される可能性はあります。
日本の場合
前述のとおり、日本では、再販売価格拘束に対して「最低価格」「最高価格」を明確に区別した上での司法判断は現在までのところ出されていません。
これまで説明してきたように、自由競争を阻害し、消費者のデメリットに繋がることから、「最低」再販売価格拘束は違法性が認められやすいと言えます。一方、「最高」再販売価格拘束はメリットの方が多いため、合法とされることが多いでしょう。
「希望小売価格」は違法なのか

商品の価格の横に「希望小売価格」という記載があるのを見たことがあるでしょう。「希望小売価格」とは、その名の通り、メーカーが希望する販売価格です。
一方、一般書籍などには「定価」という記載があります。新刊の書籍や新聞は全国で同じ値段(定価)で販売されています。これは例外的に適法として認められています。
では、「希望小売価格」は違法・合法どちらなのでしょう。司法判断について見ていきましょう。
流通・取引慣行ガイドラインでは違法性が認められる場合あり
先ほど出てきた「定価」の場合、小売店は自由な価格設定ができないのですから、出版社や新聞社による販売価格の拘束と認めざるを得ないでしょう。したがって、普通に考えれば再販売価格拘束に当たるはずですが、新刊の書籍や新聞は文化の復興に必要な商品として例外的に認められています。
希望小売価格が定価と異なるのは「拘束力」です。仮に希望小売価格に拘束力が認められる場合は、「流通・取引慣行ガイドライン」に言うところの再販売価格拘束に当たるため、独占禁止法違反に当たる恐れがあります。
しかし、希望小売価格をあくまでも「希望」とし、原則として小売業者に自由な価格設定を認めている限り、再販売価格拘束には当たらないと考えられています。
再販売価格拘束に当たる具体例
以上より、次に挙げるようなケースでは、希望小売価格が再販売価格拘束に該当すると判断される可能性が生じます。
・小売業者が希望小売価格よりも安い価格で販売することを禁止する
・希望小売価格よりも安い価格で販売している小売業者への出荷を停止、もしくは減少する
実店舗・ECサイトのどちらも司法判断は同じ
希望小売価格が再販売価格拘束と認められると、事業者(メーカー)に対し独占禁止法違反として課徴金納付命令(独占禁止法20条の5)が科されることになります。
しかし、実際のところ、希望小売価格はあくまでもメーカーが提示している「希望価格」に過ぎず、自由な価格設定が保証されていると考えて間違いありません。
また、「流通・取引慣行ガイドライン」には、実店舗とECサイトとで再販売価格拘束該当性に関する指標は異ならないことが明記されています。
実務担当者が考えるべきポイント
販売価格について何らかの指示がメーカーからされた場合、再販価格維持に抵触する可能性が高いので、メーカーに確認することが肝心です。
メーカーの指示に従った結果不当に高い値段設定となり消費者が購入を踏みとどまる事態になっては、小売業者にとってダメージが大きくなってしまいます。
しかし、その一方で、メーカーの指示を違法として無視した場合、仕入れができなくなる恐れも生じます。
残念ながら、独占禁止法に関する知識や関心が低いメーカーは存在します。違法と疑われるような行為があった場合は、メーカー側の担当者に真意を質してみましょう。
一方、メーカー側としては、流通業者を介さないダイレクトマーケティングを行うことも一つの方法として検討するべきでしょう。そうすれば、小売業者によって商品が安売りされることを防ぐことができます。
書籍・新聞などの定価販売制度(再販制度)について
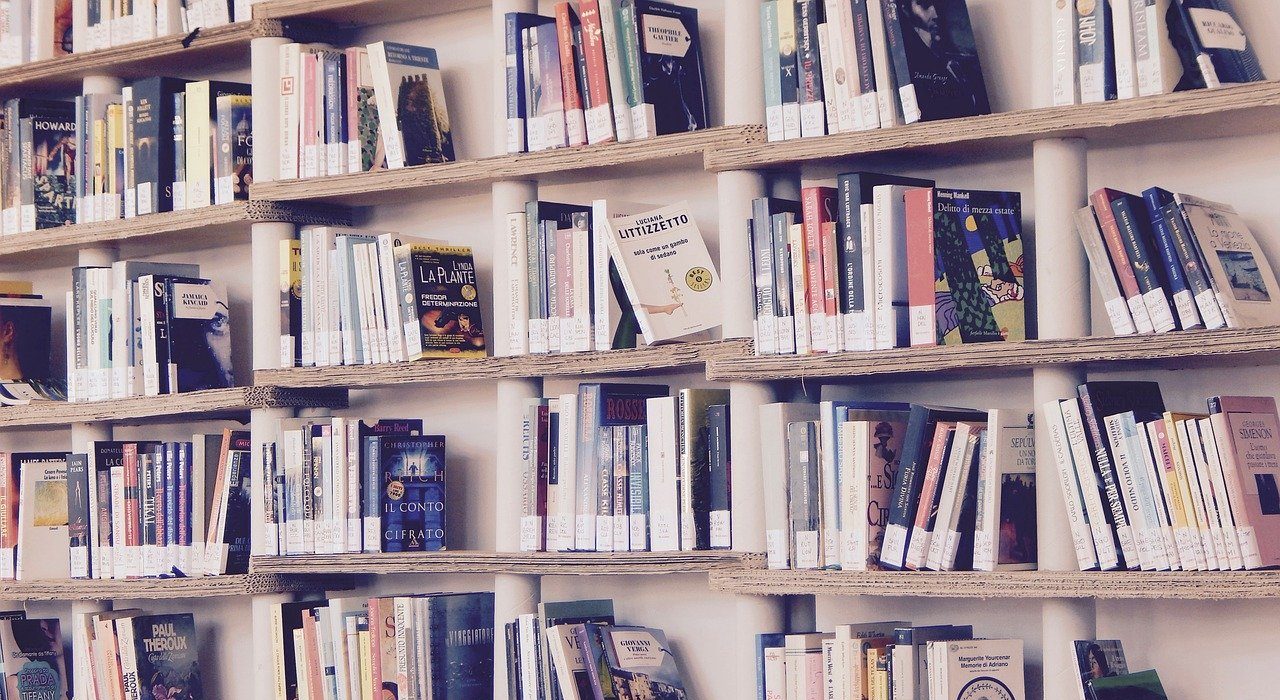
先にも触れましたが、新刊の書籍や新聞などは、独占禁止法の中で再販売価格維持行為が例外的に認められています。書籍の「再販制度」は良く耳にする言葉ですが、この制度により全国どこでも一律の価格(定価)で購入することができます。
そこで、ここからは、「再販制度」について少し詳しく見てみましょう。
著作物の再販制度とは
書籍を発行している出版社や新聞社が小売店に対して販売価格を拘束することは、例外的に認められています。これを著作物の再販制度(再販売価格維持制度)と呼びます。
著作物が例外である理由
著作物に再販制度が認められている理由は、簡単に言えば「書籍を扱う小売店が自由に価格設定を行うことを認めると、消費者が不利益を被る」と考えられるからです。
以下では、その不利益(デメリット)について説明していきます。
著作物の価格競争はデメリットばかり
小売店が書籍の価格設定を自由に行える場合、消費者は以下のデメリットを被ると考えられています。
(1)専門書の発刊が滞る
書籍の流通量は膨大です。現在では、60万点の書籍が常に市場に流通しています。その中でも新刊書籍は毎年65,000点も発行されています。消費者が専門的な書籍から一般書籍まで、トレンドに偏らずにあらゆるジャンルから本を選ぶことができるのは、再販制度によって価格が安定しているからです。
専門書籍は一般の書籍に比べ利用者が限られます。需要が少ないからといってその価格を下げてしまうと、出版社や著作者は製作コストがかけられなくなるので、結果として専門性の高い書籍は流通しなくなってしまいます。
(2)都市部と地方で値段が変わる
価格が不安定な場合、どうしても人口の多い都市部に比べ地方の方が書籍の値段が高くなりがちです。こうなると消費者にとって不公正が生まれてしまいます。
(3)書店が減る
一般的な商品と同じように価格競争が行われれば、専門書籍を扱う書店の需要は減少し、売れるトレンド書籍を扱う書店ばかりに偏ることになります。
著作物の価格
著作物には定価があるため、消費者は値段を選択することができません。そのため、高すぎるのではないかと疑う声もあることでしょう。
一般的な商品の価格は、消費者物価指数で見ると1975年から1998年までに2倍近く(1.85倍)上昇しています。しかし、著作物は同じく1988年までで1.28倍の上昇に抑えられています。
著作物には競争原理が働かないかと言えば実はそういったことはなく、出版社間での価格競争にさらされています。消費者物価指数の上昇が抑えられていることからもそれが分かります。
価格が守られるために流通量が多すぎるのではないか
「本が売れない」「返品の山」といった出版業界の窮状を耳にしたことがあるかもしれません。また、多くの方は書籍が再販制度に守られていることで供給量が需要を上回っているのではないかと考えるかもしれません。
書籍は返品されたからといって全てがゴミとして処分されるわけではありません。注文数の変動により、返品された書籍を再度出荷することも少なくないのです。
さらに、古書ルートを通して販売される場合もあります。その場合は、小売店が自由に価格を設定することになります。
再販制度がなくなる可能性について
米国をはじめとする諸外国では、著作物に対しての再販制度をすでに廃止し、小売店が自由に価格設定が行えるように制度変更されています。
日本でも過去に再販制度廃止に向けた議論がされましたが、公正取引委員会は著作物の文化的・公共的な役割を理由に2001年に制度の維持を決定しています。
ただ、今後議論が深まれば、一部の著作物に対しては自由に価格設定が可能な「部分再販」や、ある程度の期間が過ぎた書籍は自由に値段を設定できる「時限再販」など、制度の見直しがされる可能性はあります。
企業を守るためにも独占禁止法に関心を持つことが重要

企業としてコンプライアンス意識を持つことは、今や当たり前となってきています。知らないうちに独占禁止法違反行為を行ってしまった場合でも罰則が科されることに違いはありません。罰則を一度でも受けてしまうと、社会的な信用が崩れてしまいます。そうなっては、もう企業活動どころではありません。
そうならないためにも、常日頃から流通・取引慣行ガイドラインを確認したり、相談事例集を読むなりして独占禁止法に馴染んでおきましょう。