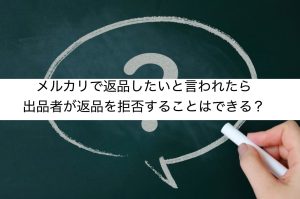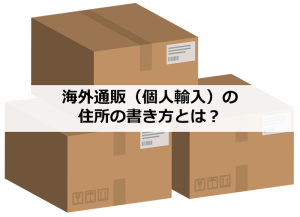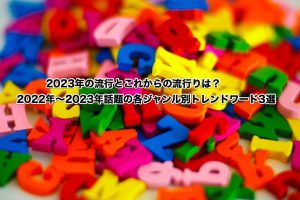商品を仕入れて仕入れ価格よりも高く販売して、それで利益を出すというのは商売の基本的な事です。その為には在庫管理やマーケティングを上手にして行く必要があり、何より大切なのは仕入れを管理する事です。
今回は仕入れ販売についてその流れや具体的な方法、目的についてご紹介します。
仕入れ管理とは何をすれば良い?

商品を販売するには仕入れをする必要があり、その知れる商品の数量や仕入れた後の管理などの業務を「仕入れ管理」と言います。仕入れ管理を上手にする事で正しく利益を出すことが可能で、商売において非常に重要なポイントです。売れる商品を仕入れる為にリサーチを行う事も、仕入れ管理の業務のうちに入ります。
仕入れ管理の流れについて
仕入れを行うにはほとんどの場合「仕入れ伝票」を作成し、卸業者に発注をしてから商品を仕入れます。仕入れ伝票には仕入れ日、仕入先、商品、単価、数量、合計金額などが記載されていて、仕入れをしてもらうのに必要な情報が記載されています。商品が納品された後は納品書と発注書に、相違が無いかを確認して仕入れ作業は完了です。
毎回きっちりと確認すればあまり間違いは起きませんが、それでも仕入れから在庫になり販売をするまでに在庫のズレが生じることがあります。その為ほとんどの事業では「棚卸し」という作業をします。
棚卸しでは仕入れた商品と販売した商品の内容を確認して、在庫にズレが無いかを確認する作業です。そのズレを限りなく少なくする為に日々の伝票管理が重要になり、明瞭な仕入れ管理が必要です。商売をする上で販売する他にこのような管理業務も重要な仕事です。
仕入れ管理の目的について
仕入れ管理を徹底して行うことができれば、無駄な発注を抑えることができ、更に管理が進めばデータを出して分析をする事も可能です。
優先すべき仕入れをデーターで割り出して多品種小ロットで仕入れを行い、必要最低限の在庫だけを持つように管理することができます。無駄を排除し効率的に仕入れ管理を行い、コストを下げる事で利益の最大化を目指します。
仕入れ管理の具体的な業務は?

仕入れ管理の具体的な業務についてご紹介します。「小売業」では商品を仕入れる必要がありますが、その商品の仕入れを管理する事を仕入れ管理と言います。また、製造業では商品を製造するための部品などを仕入れる必要があります。
それらの仕入れは商品を販売するにあたって円滑に商売が出来て、利益を出せるように管理する必要があります。具体的な流れは見積もり依頼をして、購買契約の締結を取引先と行い、発注をして、納品と検品を行い、代金の支払いをするという流れが一般的です。それぞれを詳しくご紹介します。
見積もりの依頼について
商品を仕入れる為には見積り依頼をするという作業から始まります。基本的にいくつかの仕入先に見積り依頼をして比較検討を行い、仕入れ業者を決めるというのが一般的です。
部門がいくつかに別れている会社では、製造業では商品や材料などの種類によって担当部門が購買部門へ「商品、材料、部品」が記載された依頼書を発行します。
その依頼書に基づいて仕入先を検討していきますが、その検討する内容は「価格、品質、納期、運送条件」などの内容を確認して決めていきます。具体的には下記の点について確認をします
- 安定需給の可否
- 商品品質の安定性
- 発注から入荷までの納期の確認
問題がなければ契約の締結へと進みます。
購買契約の締結について
仕入先との取引を開始する前に、取引をする時の条件を決める為に「購買契約」を締結する必要があります。取引条件とは、具体的には下記のような内容です。
- 保証
- クレーム処理
- 機密保持
- 解約
- 期間
- 支払締め日
- 支払い方法
このような条件を決めていきます。
これは取引後のトラブルを防ぐ為に、詳細な内容を決めておくのが一般的です。購買契約の締結を終えた後は「仕入先台帳」を作成して、自分自身で仕入れの詳細な内容を記録しておきます。
発注業務について
先ほどの工程で決定した仕入先に、自分が欲しい商品を発注するのが「発注業務」です。発注業務の内容は大きく3つに分かれます。
- 購買依頼書の作成
- 仕入先の選定
- 注文書の作成
まず購買依頼書とは購買するべきものを在庫を確認してから取り決めて、購入する事を依頼する書類です。発注業務が別部署の場合に必要になります。
内容は作成日や目的、商品、納期などを記載します。仕入れるものを決めてから次は仕入先を選定し納期や数量、価格などを比較検討します。最後に注文書には発注日や納期、商品、金額などを記載して注文内容の詳細を記載します。
入荷と検収業務について
発注した商品が指定した納入場所に納品されたら、次は入荷と検収業務があります。この工程は大きく4つに分かれます。
- 入荷品の検収
- 検収結果の報告
- 伝票の作成
- 取引内容の記帳
まず商品が納品された時には納品書や受領書を受け取り、余裕があれば発注書との相違が無いかをその場でチェックします。
到着した商品の数量や品質などを確認するのが「検収」という業務で、その後には他部署に報告が必要なら検収報告書を作成します。最後には伝票を整理した後に取引内容の記帳をして、仕入れや出荷の詳細を記録する「商品有高帳」を作成して完了です。
仕入れを計上する基準について
発注した物をどのタイミングで自社の在庫として計上するかは、業種や取引形態によって異なります。このことは「仕入れ計上基準」と呼び、その会社の状況にあった基準が設けられています。
大きく分けて下記の3つの基準があります。
- 発送した日
- 入荷した日
- 検収した日
発送した日を基準とする方法は継続的に商品を出荷する物販業で採用されています。多くの会社では入荷した日を基準としていて、品質を重視している会社は検収した日を基準にしています。
支払い締め業務について
仕入れた商品の支払い処理を行う業務を「支払い締め業務」と呼びます。取引の都度支払いを行うパターンと一定の期間を決めて集計した分を支払いをするパターンです。
その都度支払いをする場合や1度だけの取引や個別にサービスを受ける場合は、請求書を受けとり支払いを行います。もう一方の一定期間を決めて集計して支払う場合は継続して契約を行う場合に用いられて取引条件を設定して、仕入れ締め日に集計をします。
この時に発行される請求書の内容の金額を、今までの請求書で確認することを「支払いの締め切り」と呼びます。経理担当がいる会社であれば金額が確定したら「支払い依頼書」を作成して経理担当に引き渡します。
支払い業務について
仕入れた物の代金を仕入先に支払うことを「支払い業務」と呼び、ここでは下記4点の業務を行います。
- 支払い予定表の作成
- 支払い振込作業
- 支払いの記帳
- 出金の消し込み
支払い予定表とは経理担当者が受け取った依頼書や仕入先から受け取った請求書を見て、支払い予定表を作成します。この支払い予定表とは仕入先からの請求情報や取引内容、請求の支払日などの情報を一覧で確認できる表です。この予定表を作成することで資金管理が容易になり、ミスが少なくなります。
次に振込作業を行いますが、最近では取引銀行と提携してオンラインで処理をしている会社も多いです。ファームバンキングと呼ばれる仕組みは作業を簡略化できるので件数が多いならぜひ取り入れてください。2024年1月以降、ファームバンキングに使用されているISDN回線が順次提供終了となり、従来のファームバンキングは2023年内に終了します。各銀行で代替サービスが提供されていますので、これから導入を考えている方や既に利用している方も、利用している銀行の代替サービスを確認しましょう。
支払い内容の記帳には支払いを期日までに行い、その内容を出金伝票に記帳します。内容としては出金日、仕入先、支払い方法と金額などを記録しておきます。
最後に「消し込み」という作業を行います。これは過去の取引と出金金額を確認して、どの取引の出金をしたのかを確認します。
仕入れをする取引形態は何がある?

仕入先への取引をする時の取引形態は大きく分けて3つに分けられて「現金」「掛け(都度)」「掛け(締め)」があります。それぞれの詳細をご紹介します。
現金取引について
仕入先から納品した代金の支払いに現金を使用する取引形態で、領収書を発行してもらい保管しておく必要があります。振込などの処理が必要ないので、その場で取引が完了します。
都度行う取引について
これは取引がある度に請求される取引形態で、仕入先から受け取る請求書には支払い期日や支払い方法が記載されています。その内容に従って処理を進めていきます。
締め日を設定してまとめて行う取引について
仕入れをした代金の締め日を設定して、期間分の納品代金をまとめて支払う取引形態です。ある一定以上の取引が継続して行われる必要がありますが、請求書の発行や支払い業務が少なく済むので、手間が省けます。この期間は1ヶ月に設定することが多いですが、それ以上の場合は「繰越金額」として未入金になっている分を請求書に記載する場合が多いです。
仕入れにはどんな形態がある?

仕入れには、形態別に「買取」「委託」「消化」があります。それぞれの形態の内容と特徴をまとめてご紹介します。商品を仕入れて販売する時には個人でも、この取引に分けることができますので参考にしてください。
買取仕入れについて
この仕入れについては店舗が仕入先から買い取って販売する方法で、卸業者から商品を買い取るのがこの形態です。この形態では発注の精度が高ければ売れる商品を売れるだけ仕入れることができるので無駄が少なく済みます。
ただ商品は買取で返品ができないため、売れない場合は店舗在庫として抱える事になります。商品が売れないと仕入れる為の資金も循環できないので、売れない商品を仕入れた時の事も想定する必要があります。
委託仕入れについて
先ほどの買取と比べて売れなかった時のリスクが少ないのがこの形態で、販売委託契約という形で店舗に商品を置き、商品の売上げの数%を仕入れ業者がもらうという内容です。
売れた時の利益は若干減りますが、売れ残った商品については返品が可能で定期的に商品を循環できるのでリスクが少ないのが特徴です。商品を受け取った時点で「仮仕入れ」というような状態になるのがこの形態の特徴です。
消化仕入れについて
委託仕入れと似ていますが、この仕入れ形態は商品が売れて初めて仕入れ処理を行います。その為商品が届いた時点では店舗での処理は何もせずに、そのまま販売するという事になります。
商品の販売が確定するまではメーカーの在庫として数えて、売れなければそのままメーカーに返すだけという契約形態です。ローリスクで自由度は高いですが、その分ローリターンという契約内容がほとんどです。
珍しい仕入れ方法は?

仕入れという業務の中には、その内容が珍しいものもあります。通常の仕入れとは一風違った仕入れ方法をご紹介します。
ドロップシッピングについて
メーカー直送と呼ばれるこの「ドロップシッピング」という仕入れ方法は、注文が入った時点でメーカー倉庫から直接購入者へ届けるという手順です。販売するお店では在庫を持たずに、仕入先から直接届けるのでショップ運営者の仕入れはデーター上の数字が動くだけで実際には動きません。
そのため、パソコンだけで作業ができるという特徴があります。手間の少ないビジネス手段ですが、メーカーとしては買取の方が都合が良いので手数料がかかる場合がほとんどです。
サヤ取りネットビジネスについて
ネット上では同じ商品が色々なショップで販売されていますが、差額がある商品を見つけて価格差の分を稼ぐという仕入れ形態です。
例えばアマゾンでは5000円の商品がヤフーショップでは3000円で売っている場合、ヤフーショップで仕入れてアマゾンで売れば2000円分の利益を手にすることができます。国内のショップだけではなく海外まで視野を広げるともっと大きな価格差が広がってる事もあります。
この手法ではリサーチ力がとても重要なので、どの商品をリサーチするかはその為に情報をあつめて効率よく仕入れる事が大切です。人の手でリサーチする方もいますし、クローラーを用いる事もありますが専門的な知識が必要になります。
まとめ

「売る為の商品を仕入れる」という事は商売をする上でとても基本的な事ですがその手法や形態は様々です。今回ご紹介した内容を参考にして、自分にあった手法を見つけて仕入れの作業をスムーズに行いましょう!