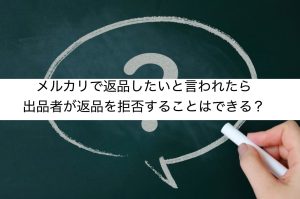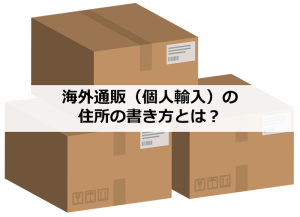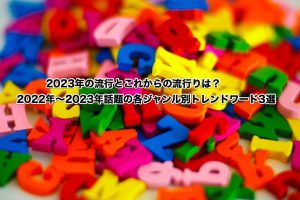輸出入事業をする上でネックとなるのは、その仕訳方法になります。売上計上のタイミングや関税・消費税の扱いには注意が必要です。
そこで今回は、輸出入事業者に向けて、必要となる勘定科目と、仕訳するタイミングなどについて解説します。
輸出入をする際の貿易条件とは

輸出入をする際は海外の税法についても知る必要があります。しかし取引によっては海外の税法に関係なく、日本の税法のみが適用される取引もあります。
その場合日本の税法のみを知っていれば良いのですが、売上計上する上では、輸出入に関する基礎知識が必要になります。
最初に貿易条件の決め方と、代表的な貿易条件を紹介します。
貿易条件について
国や地域によっては貿易における用語の意味や慣習が異なり、トラブルになりかねません。そのため貿易条件を国際的に定める必要があります。
貿易条件を統一することで、貿易をする際に生じる紛争や混乱を回避することができます。
このように貿易条件について定めた国際規則をインコタームズと言います。次にインコタームズについて解説します。
インコタームズ
インコタームズとは、世界共通で使える貿易条件のテンプレートです。
・どちらが通関費用を負担するか?
・どちらが関税、消費税の負担をするか?
・どちらが配送料の負担をするか?
・どこまでが輸出者の責任になるのか?
などに関する細かい条件がインコタームズで定められています。細かい貿易条件を取り決める際は、個別に交渉せずに「インコタームズの◯◯を採用します。」と伝えるのが一般的です。
よく使われるインコタームズを3つ紹介します。
FOB(Free On Board)
FOBは、船積み前は輸出者が、船積み後は輸入者が輸送料・保険料を負担するタイプのインコタームズです。貨物は船上で引き渡されます。
CFR(Cost and Freight)
CFRは輸出者が輸入港までの輸送料を全て負担して、輸入者は船積み後の保険料のみを負担するインコタームズです。FOB同様、貨物は船上で引き渡されます。
CIF(Cost,Insurance and Freight)
CIFは輸入港までの輸送料・保険料を全て輸出者が負担するインコタームズです。輸入者が負担するのは輸入港到着後の費用のみです。
輸出入事業における関税
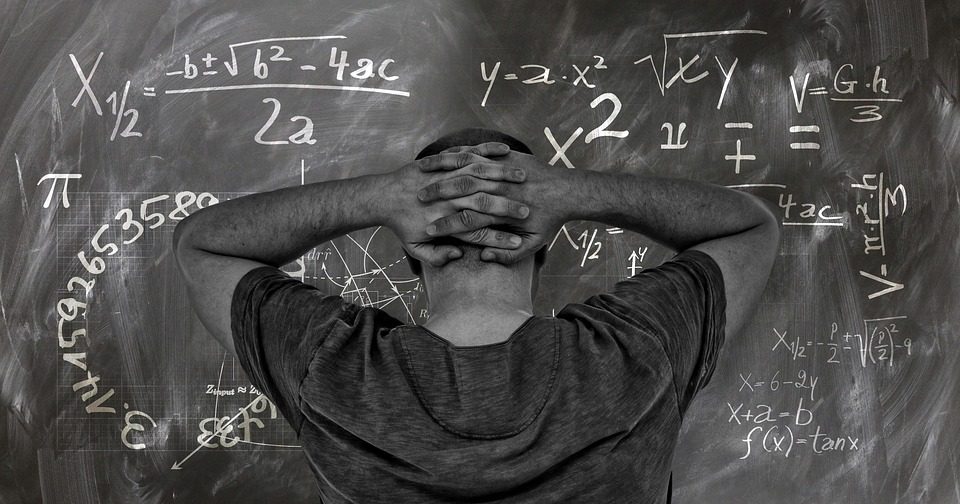
輸出入事業における関税はどうなっているのかを解説します。
関税とは
関税とは、国境を超える際に発生する税金になります。輸出入、どちらにも発生しますが、一般的には輸入時の輸入関税のことを言います。
輸入品に関税があることにより、輸入品の仕入額が上あがり、それにともない販売価格も上がります。そのため、国内製品の優位性が保てるのです。
関税と輸入消費税
関税と輸入消費税は似ているようで異なった税金になります。
関税は、輸入者が支払う義務のある税金となります。そのため、関税は支払った時点で費用換算され、仕入れの費用として計上されます。
輸入消費税も同様に輸入者が支払う義務のある税金ですが、こちらは消費税という税金の特徴から、少々異なった計上となります。
消費税とは、自分が使用するために購入する際の納税義務であり、最終的な購入者に届くまでの中間業者に発生する税金ではありません。そのため、今回の場合でいう輸入者にとっては、費用計上とはならず、仮勘定という扱いになります。
仮勘定という勘定科目は、年度末の確定申告の際に精算され、収益あるいは費用と換算されるのです。つまり、輸入消費税は年度末の確定申告の際に費用として計上されることになります。
海外取引の会計処理
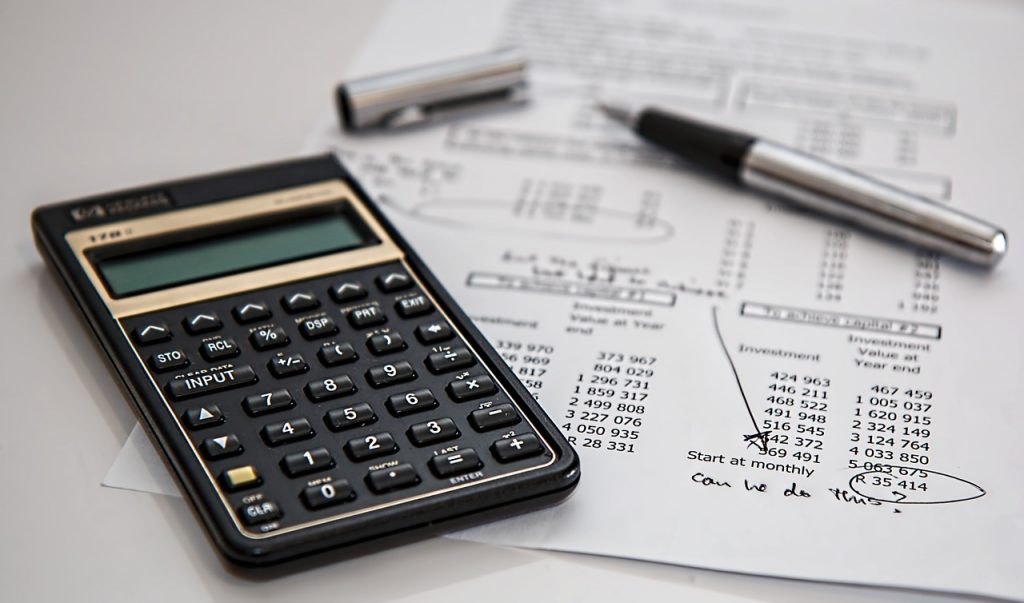
輸出入取引の勘定科目や仕訳のコツを解説します。
輸入取引の勘定科目
輸入取引の場合、商品代金・送料・保険料・関税・通関手数料などの勘定科目は、全て「仕入・仕入高」とするのが一般的です。
ただし、消費税だけは会計処理の仕方によって勘定科目が異なります。税抜処理をしている場合は「仮払消費税」、税込処理をしている場合は「仕入」とします。
輸入仕入れの計上時期
国内仕入れの場合は、商品を受け取った時点で仕入れとして計上するのが一般的です。
しかし、輸入仕入れの場合は貿易条件によって計上時期は異なります。一般的には相手国側で船積みが完了した時点を基準とするケースが多く見られます。
輸出売上の計上時期
輸出売上の計上時期としては、以下の5パターンが考えられます。
1.自社からの出荷日
2.船舶や航空機に積み込まれた日
3.通関日
4.船荷証券(B/L)作成日
5.輸入国側で陸揚げされた日
海外取引の際の仕訳

海外取引の際、特に輸入時などの勘定科目の仕訳方法について説明します。
注文時
注文の際には物品などに動きがないため、仕訳はありません。
船積時
輸入の場合、輸出先で製品が船に積まれるときに計上するのが一般的となっています。
船に積む際に、輸入国側で借方科目に仕入、貸方科目に買掛金の仕訳を切ることになります。
輸入通関時
製品が税関を通る際には、輸入の許可とともに関税と輸入消費税の納付が義務となっています。この際に借方科目に仕入(関税)、仮払消費税等(輸入消費税)を、貸方科目に現金の仕訳を切ることになります。
支払時
銀行振込による代金の支払い時は、借方科目に買掛金、貸方科目に普通預金の仕訳を切ることになります。
仕入の計上は、輸出者が船積したとき
前述しましたが、国内取引とはことなり、輸入時などにおける仕入の計上は輸出国側で船積する際に計上するのが一般的です。
これは、製品所有の際のリスクと経済価値が変わったときに仕入れ計上を行う、という考え方があり、それが船積時ということになるからです。
海外取引と消費税
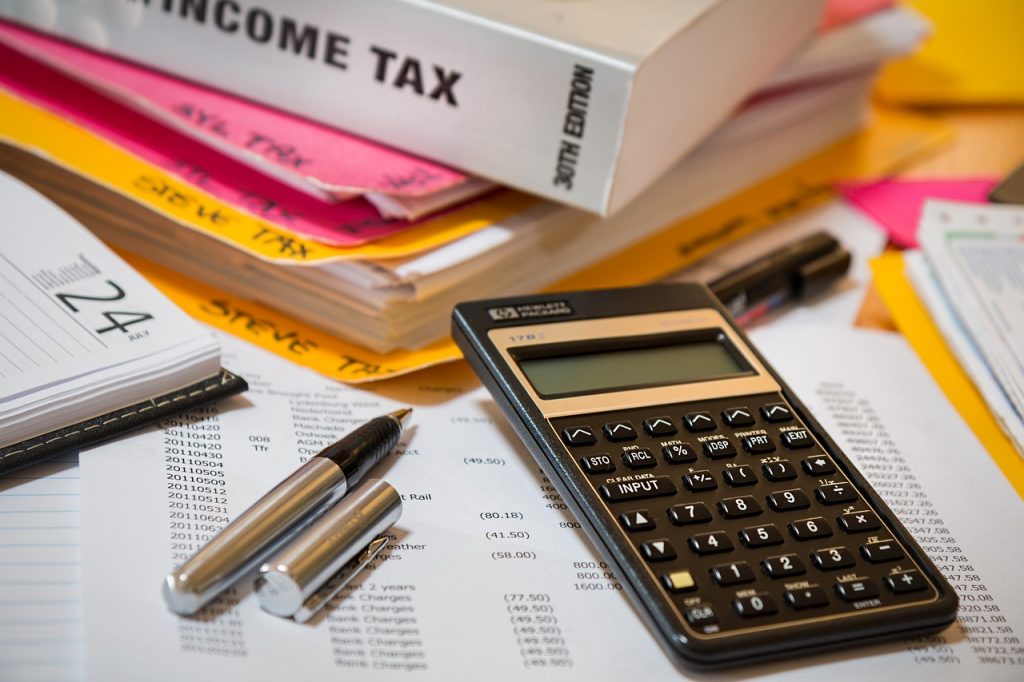
消費税とは、消費者が商品・サービスを購入した際に発生する標準税率10%(2021年3月時点)の税金と、お酒や外食を除いた飲食料品や、定期購買契約され週に2回以上発行される新聞に発生する軽減税率8%(2021年3月時点)の税金のことです。本来消費税の納付義務があるのは消費者です。
しかし、消費者一人ひとりが各自で納税するのでは手間がかかってしまうため、日本では商品・サービスを販売している事業者が消費者から消費税に相当する金額を預かり、後でまとめて納付することになっています。
ただし、仕入れや外注などで取引先に消費税を支払っている場合は、事業者は消費者から預かった消費税額から仕入先・外注先に支払った消費税額を引いた差額を納付すれば良いことになっています。
輸出売上の消費税
消費税は物やサービスを消費したことに対する課税なので、本来は消費者が負担すべき税金です。しかし、海外輸出の場合は消費者が海外にいるため、消費税を消費者から徴収することができません。
その一方で、輸出事業者は国内で商品を仕入れる際に消費税を支払っています。このままだと、消費者でない輸出事業者が消費税を負担することになってしまいます。これは消費税の趣旨に反します。そこで、輸出事業者が自己負担した消費税相当額は返還される仕組みになっており、これが消費税還付と呼ばれるものです。
輸出事業者の消費税還付手続き
日本では消費税の納付義務を負うのは、2年前の売上が1,000万円以上の事業者だけです。2年前の売上が1,000万円未満の場合は、消費税納付の義務がない「免税事業者」となります。
免税事業者は課税対象者でないため、消費税還付を受ける権利もありません。
しかし、2年前の売上が1,000万円未満の事業者でも消費税還付を受ける方法はあります。それは課税事業者になることです。自ら申告して消費税を納めれば課税事業者になることはできます。課税事業者になれば、売上額が1,000万円未満でも消費税の還付を受けられるようになります。
まずは最寄りの税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出してください。
ただし、提出してすぐに課税事業者になるわけではありません。課税事業者になれるのは提出した日の含まれる事業年度の次の年度からです。
課税事業者になったら、あとは消費税の確定申告をすれば消費税還付を受けることができます。
輸入仕入れの消費税
逆に海外から輸入する際は、仕入先に支払うのは商品代金のみで、消費税は支払いません。そうなると、消費税がかからない分、国内から仕入れるより海外から仕入れる方が安くなる可能性があります。
輸入した方が安いとなれば、国内から仕入れる業者が減り、国内産業が停滞する恐れがあります。このような不都合を避けるために、輸入者には輸入消費税が課せられています。
輸入消費税は、海外から輸入した商品を保税地域(輸入貨物の保管場所)から引き取る際に支払う必要があります。
消費税が免除される取引

消費税が免除されるのは、非課税取引・国外取引・免税取引の3つです。
非課税取引
輸入した商品が以下のような非課税商品である場合は、輸入消費税が免除されます。
・有価証券(外国為替含む)
・郵便切手類
・印紙
・証紙
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等
・身体障害者用物品
・教科用図書
国外取引
輸出する場合、日本人や日本企業相手の取引でも取引相手が国外にいれば「国外取引」となり、消費税還付を受けることができます。
しかし、外国人や海外の企業を相手に取引をしていても、取引相手が国内にいる場合は「国内取引」とみなされます。
輸出免税取引
ただし、国内取引でも以下のような輸出免税取引に該当する場合は、国外取引同様、消費税還付を受けることができます。
1.日本から海外への一般的な輸出
2.外国貨物の譲渡・レンタル
3.外国貨物等にかかる運送・保管などのサービス提供
4.国際配送・通信サービスの提供
5.外航船舶等の譲渡・レンタル・修理サービスの提供
6.日本に住所を持たない訪日外国人への販売
輸出免税と判断しにくい取引
輸出免税取引として認められる取引には様々ありますが、中には輸出免税の対象なのか判断しにくい取引もあります。輸出免税対象取引とそうでないものの具体例を挙げておきます。
【輸出免税の対象】
・輸入商品を保税地域から直接海外へ輸出
・国際配送に含まれる国内配送サービス
【輸出免税の対象外】
・輸出商品の製造、下請け加工
・保税地域内の保管サービス
消費税に関する用語解説

不課税・非課税・免税はよく似た言葉ですが、意味が少し異なります。
不課税取引
そもそも消費税の課税対象ではない取引を指します。
非課税取引
消費税の課税対象ではあるものの、消費に負担を求める税として性質上や社会政策的配慮から課税対象外に設定された取引を指します。
免税取引
国内取引ではあるものの、海外取引と同様に消費税が免除された取引を指します。
例えば、商品の輸出や海外輸送、外国にある事業者へのサービスの提供といった輸出類似取引などがこれにあたります。
海外取引は会計処理が面倒

海外取引では勘定科目の仕訳タイミングや税金の扱いが国内取引と異なるため面倒だと感じてしまいますが、輸出入事業を円滑に行うには会計処理や税金に関する知識が欠かせません。
是非、こちらの記事で学んだことを実務で活かして下さい。