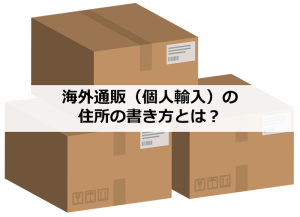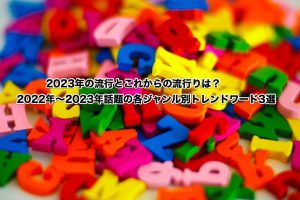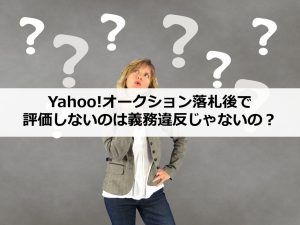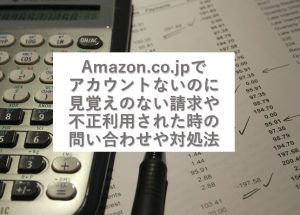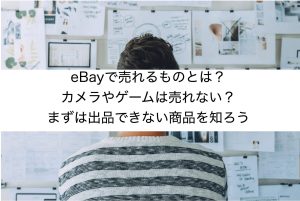最近、個人輸入をする人が増えています。中には、海外の通販サイトで気に入った洋服を個人輸入したいという人もいらっしゃるでしょう。
しかし、輸入には「関税」がつきものです。「関税」と聞くと、難しくて取っつきにくいというイメージを持つ人もいるでしょう。
そこで今回は、洋服を輸入する際の関税についてまとめました。具体的には、関税の意味や仕組み、計算方法、支払い方法などを解説します。
これを読めば、洋服を個人輸入する時にも役立つはずです。ぜひ参考にして下さい。
関税の意味、仕組み、計算方法は?
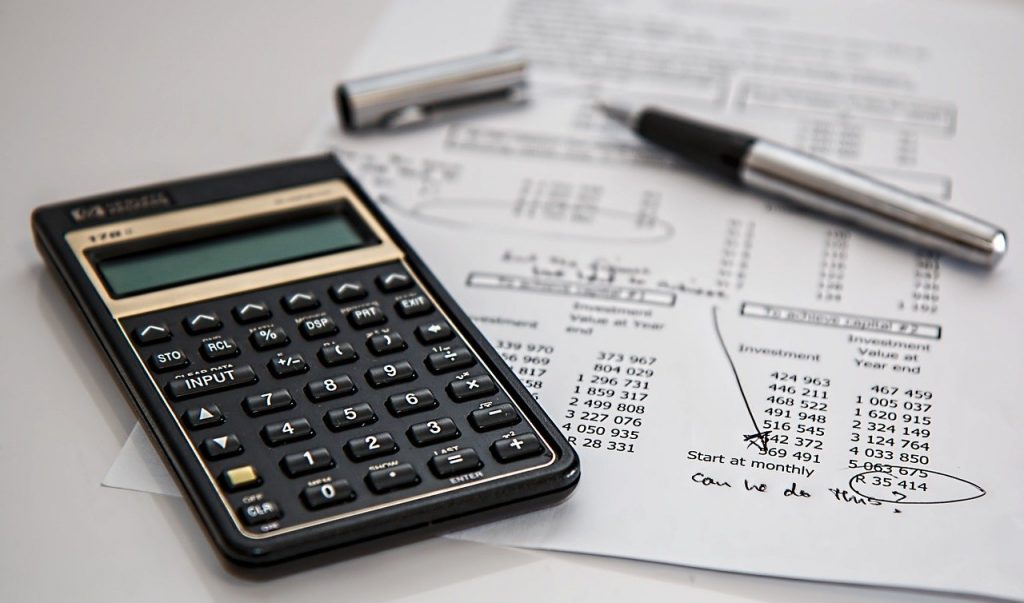
個人輸入を行う際には、2種類の税金がかかります。それが「消費税」と「関税」です。消費税は馴染みのある税金ですが、関税については「よくわからない」という人も多いかもしれません。早速、それぞれの税金について順番に見ていきましょう。
消費税とは?
消費税は、商品やサービスを購入した際にかかる税金です。国内で商品を購入する時だけでなく、海外から商品を輸入する際にも課せられます。
消費税の税率は10%ですが、その内訳は次のとおりです。
・消費税率:7.8%
・地方消費税率:2.2%
最終的には消費者が負担することになる税金ですが、制度上は事業者が集めて納税する仕組みになっています。
参考:消費税のしくみ|国税庁
関税とは?
関税は、海外から商品を輸入する際にかかる税金です。商品の種類や金額により税率や税額は異なります。詳しくは「別表」というかたちで定められており、「関税率表」を見れば税率がわかるようになっています。
また、「軽減税率」のように、商品によっては特例が適用される場合もあります。
「関税」制度の目的は?
関税が設けられているのは、国内の産業を保護・育成するためです。
安価な輸入品が大量に国内に流入してしまうと、価格競争力の差から自国産業が衰退してしまう可能性があります。このような事態を防ぐために、関税制度が設けられているのです。
「関税」はどのようにして決まる?
関税はその国のルールによって定められます。
なお、「環太平洋パートナーシップ協定」(TPP)や「自由貿易協定」(FTA)、「経済連携協定」(EPA)などの貿易協定に加盟している国同士であれば、無税にする等の特典が設けられていることもあります。
また、販売目的での輸入なのか、個人利用目的での輸入なのかによっても税率が変わってきます。具体的な関税制度は複雑なところもありますが、まずは大枠のルールを押さえておけば大丈夫です。
関税の計算方法は?
関税額を計算するにあたっては、以下の計算式が用いられます。
・関税額 = 課税対象額 × 関税率
・課税対象額 = 商品代金 × 60%(個人利用目的で輸入する場合)
たとえば2万円の傘を輸入するとします。この場合の具体的な関税額は次のようにして算出されます。
・課税対象額 = 20,000円 × 60% = 12,000円
・関税額 = 12,000円 × 関税率(傘は6.4%) = 768円
いろいろな特例によって実際の関税額は微妙に異なってきますが、基本的には以上のようになります。
関税の「免税措置」とは?
輸入に際しては「免税措置」が設けられている場合もあります。基本的には「一度に梱包される商品の合計課税対象額が1万円以下で、かつ、個人利用目的の場合は免税」となっています。
つまり、課税対象額が16,666円以下で、かつ、個人利用目的なら免税ということです(前述の個人利用目的の場合の関税額の計算方法を思い出してください)。
なお、免税対象外の商品もあるので要注意です。たとえば、革製品や編物、履物などは、免税対象外となっています。
参考:課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー)|税関 Japan Customs
洋服の個人輸入!必要な関税や手数料は?

関税の仕組みや計算方法を概観したところで、今度は個人輸入で必要となる税金や手数料、簡易税率などについて説明します。
個人輸入で必要となる税金と手数料は?
日本国内で通販を利用して商品を購入する場合、一般的には、商品金額と消費税、そして送料だけの負担で済ませることができます。
しかし、個人輸入する際は、これらに加え「関税」と「通関手数料」がかかるので、
・商品金額
・送料
・消費税
・関税
・通関手数料
のすべてを負担しなければなりません。
「簡易税率」とは?
また「簡易税率」という制度もあるので覚えておきましょう。
通常の場合、関税率の計算には「一般税率」が適用されます。数千種類もの品目分類表の中から具体的な税率を特定することになります。他方、より簡便に計算できるように設けられたのが「簡易税率」です。
「簡易税率」を適用する場合、税額は7品目の分類表に基づき簡易に算出されます。ただし条件があり、これが適用されるのは、課税価額の合計が「1万円超かつ20万円以下の場合」に限られています。
なお「簡易税率」を希望しない場合は「一般税率」を選択する事も可能です。
参考:少額輸入貨物の簡易税率|税関 Japan Customs
この「簡易税率」を選ぶ場合、「一般税率」に比べてどう変わるのでしょうか。
「簡易税率」なら、たとえば衣類なら10%の税率という特例が定められています。具体的に2万円の洋服を輸入する場合を計算してみましょう。
課税対象額は「20,000円 × 60% = 12,000円」となるので、関税額は「12,000円 × 関税率(特例で衣類10%) = 1,200円」となります(個人使用目的で輸入した場合)。
これに対して一般税率の場合は、商品によって税率が変わります。実際に税率の比較をしてみたい方は、ぜひ以下のページを参照して下さい。
参考:第61類|衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る)の税率
参考:第62類|衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く)の税率
立替納税手数料とは?
なお、忘れてはならないのが「立替納税手数料」の存在です。
商品を輸入するにあたり、税関での諸手続きを実際に担っているのは「国際運送会社」です。そして、その手数料として支払うのが「立替納税手数料」です。
運送会社によって異なりますが、主な会社の手数料は次のとおりです。
| 運送会社 | 手数料 |
|---|---|
| 日本郵便(国際郵便) | 1,200円または名宛国において課された貨物の関税等額の3パーセントのいずれか高い方 |
| UPS | 1,060円または 立て替えた金額の2.1%のいずれか大きい方 |
| フェデックス | 1,000円または関税その他税金の2%のいずれか大きい方 |
| DHL | 1,100円または立替額の2%のいずれか 高い方 |
服の輸入で活用したい、関税の「簡易税率」とは?

「簡易税率」は「課税価額の合計が1万円超、かつ、20万円以下の場合」に適用されるものですが、ここからはその簡易税率についてより詳しく解説します。
参考:少額輸入貨物の簡易税率|税関 Japan Customs
簡易税率よりも一般税率で算出したほうが関税が安くなる?
輸入する商品の種類によっては、一般税率で計算するほうが簡易税率で計算するよりも税額が安くなる場合があります。
たとえば、コーヒーをアメリカから輸入する場合の税率は以下のようになります。
・簡易税率:15%
・一般税率:12%
簡易税率を適用すると15%ですが、一般税率なら12%で済ませることが可能です。
関税がかからないケースがある?
たまに「関税がかからなかった!」という声を耳にすることがあるかもしれません。これは、偶然にもチェックを免れた場合です。
滅多にないことですが、「国際郵便」ではこうしたことも起こります。しかし、ヤマト運輸の「国際宅急便」を利用した場合は、このような事態が起きることはありません。なぜなら、全ての商品がチェックされているためです。
関税の納税方法は?
簡易税率が適用される場合の納税方法について見ておきましょう。
「国際宅急便」でも「国際郵便」でも、荷物の受け取り時に支払うことになります(配達員が持参する「費用明細」をチェックしてください)。
なお、FedexやUPS等を使った場合は、配達時ではなく、後日なされる請求時に支払うこともあります。
洋服の輸入でチェックすべき関税分類「61類、62類、63類」とは?

ところで、服や衣類の関税は、「61類」「62類」「63類」が適用されます。
このうち新品の場合が「61類」か「62類」のいずれかで、中古の場合が「63類」です。また、「メリヤス編み」と「クロセ編み」(ニットのこと)については、「61類」ですが、そうでない場合は「62類」です。
クロセ編みとメリヤス編みはニットのこと!
まずは、クロセ編みとメリヤス編みについてです。これはニットのことを指しています。靴下やストッキングなど、伸び縮みできる素材のことです。
「61類」「62類」「63類」の分類を見る上で重要な点は、ニット製品(クロセ編みやメリヤス編み)の生地からできているかどうかで、以下のような分類となっています。
| 61類 | 新品で、ニット製品の生地で作られている衣類(クロセ編みやメリヤス編み)の場合 |
| 62類 | 新品で、上記以外の場合 |
| 63類 | ニットかどうかに関係なく、中古の衣類の場合 |
詳しく見ていくことにしましょう。
「61類」とは?
「61類」は、ニット生地による衣類の場合に適用されます。関税率は5.6%から16%となっています。
注意すべき点は、クロセ編みとメリヤス編みに限られていることです。一般的なセーターや、靴下などの下着類なら多くの商品が「61類」に分類されます。
「62類」とは?
「62類」はニット生地によらない衣類や、クロセ編みとメリヤス編みでないケースに適用されます。関税率は4.4%から16%です。
「63類」とは?
「63類」は、中古の衣類の場合に適用されます。関税率は3.9%から9.6%です。
「63類」は「紡織用繊維の物品」と定義されており、ニットかどうか、クロセ編みやメリヤス編みかどうかは関係がありません。ナイロンや綿といった布全般に適用されます。
なお、革製品については適用から除外されるので注意しましょう。
「類」の内容を確認する方法は?
様々な「類」がありますが、それぞれの内容を確認するにはどうしたら良いのでしょうか。わかりやすい方法は、税関のウェブサイトからチェックすることです。
参考:輸入統計品目表(実行関税率表)|税関 Japan Customs
「実行関税率表」の「類注」をクリックすると、類ごとの定義がPDFファイルで表示されるようになっています。
参考:実行関税率表(2023年4月1日版)|税関 Japan Customs
これを見れば、「61類」「62類」「63類」のどれに該当するかがわかるようになっています。
「簡易税率」を適用する場合は?
関税には「簡易税率」制度がありますが、「衣類」の場合はどう適用されるのでしょうか。まず適用されるのは「課税価額の合計が1万円以上で20万円以下の場合」です。類ごとの税率の分類は次のとおりです。
| 類 | 簡易税率区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 61類 | 7 | 5% |
| 62類 | 4 | 10% |
| 63類 | 7 | 5% |
「一般税率」を適用する場合は?
「簡易税率」が適用されるには、課税価額合計が20万円以下である必要があります。20万円を超える場合は「簡易税率」ではなく「一般税率」が適用されます。
「一般税率」の場合は次の6つの項目から判断します。「簡易税率」よりも複雑なので要注意です。
(1) 商品の材質は?
(2) 商品の織り方や編み方は?
(3) 刺繍の有無は?
(4) 男性用か?女性用か?
(5) 商品の利用用途は?
(6) 商品の生産国は?
参考:関税率表解説・分類例規|税関 Japan Customs
(1) 商品の材質は?
まず「天然系」か「化学系」かで区分されます。また、両方を配合した「紡織用繊維」の場合は、配合率を確認する必要があります。
(2) 商品の織り方や編み方は?
商品の衣類をチェックしましょう。織り方や編み方によって変わります。
(3) 刺繍の有無は?
商品の一部に「刺繍」があるか無いかを確認します。
(4) 男性用か?女性用か?
男性用の商品か、女性用の商品かを確認してください。
(5) 商品の利用用途は?
その商品を利用する用途はどんなものでしょうか?
(6) 商品の生産国は?
もし相手国が「EPA」(経済連携協定)の協定国なら、関税撤廃商品に衣類が含まれている可能性があります。対象となる国を原産国とする衣類なら、無税あるいは税率軽減の対象になります。
EPA締約国を調べた上で「できるだけその国から仕入れるようにする」のも一つのやり方です。
なお衣類の関税率については、次のサイトでチェックすることができます。大まかな数字を把握するのに役立ちます。無料なので、ぜひ確認してみて下さい。
参考:【小口・一般共通】衣類 / 服の関税計算ツール|HUNADE EPA/輸出入/国際物流
また、詳細に知りたい場合は、税関の「事前教示制度」を利用するのもおすすめです。
参考:輸出入通関手続きの便利な制度|税関 Japan Customs
服をお得に輸入したいなら「関税」の仕組みを理解しよう!

関税について、特に衣服に焦点をしぼって解説をしてきました。まとめると、輸入商品の合計金額によって、以下の3つに分類されます。
| 免税 | 課税価額の合計が1万円以下の場合 |
| 簡易税率 | 課税価額の合計が1万円超、20万円以下の場合(衣類は5%か10%) |
| 一般税率 | 課税価額の合計が20万円を超える場合(衣類は61類〜63類のいずれか) |
また、洋服の輸入なら、「61類」「62類」「63類」についても要チェックです。
なお、税率に関する法改正は頻繁に行われるので、詳しいことは税関の公式サイトで確認するようにしましょう。