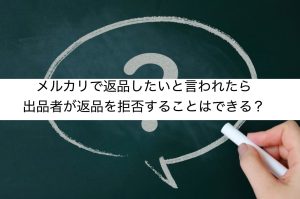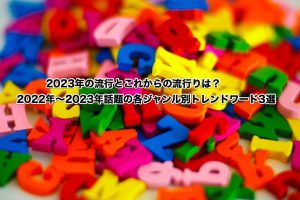メルカリで販売を行う上で非常に重要となる、商品タイトルや商品紹介文の書き方のポイントを解説します。また、メルカリ出品に慣れていない人でも使える商品説明分や説明書などを同梱する際のコメント例文やテンプレート、メルカリでの取引を行う際に重要となるメッセージの使い方や受取評価のリクエスト方法などもあわせてご紹介します。
メルカリで出品を行う際のポイント

メルカリでは不要になったものを簡単に販売することができます。
販売する商品の
・タイトル
・商品説明文
・商品の状態
を記入する必要がありますが、ポイントを押さえれば簡単にできますので、ぜひメルカリ出品の参考にしてください。
商品タイトルは正確に記入する
メルカリで商品を出品する場合、まず初めにタイトルをつける必要があります。
メルカリでは膨大な数の商品が絶えず出品され続けており、現実に開かれているフリーマーケットのように、購入者がすべての商品を見てくれるわけではありません。
そのため、商品タイトルはメルカリで商品を出品する上で非常に重要になります。商品名に誤字脱字があると、メルカリでの検索に引っかからず閲覧さえしてもらえません。
たまに通販のように「安い! 値下げしました! 〇〇 きれいなお品です!」といった、長いタイトルを付ける方もいますが、メルカリでは可能な限りタイトルはシンプルに記入しましょう。
商品の状態を選択する
メルカリで商品を出品する場合、商品の状態を選択する必要があります。
多くの場合、
・新品、未使用
・未使用に近い
・目立った傷や汚れなし
・やや傷や汚れあり
・傷や汚れあり
・全体的に状態が悪い
といった状態がメルカリでは選択できるようになっています。
ここで注意してほしいのが、「新品」と「未使用」の違いです。メルカリでは商品のジャンルによっては同義で使用される場合もあります。
しかし、洋服やクツなどタグの付いている商品においては、新品と未開封は大きく異なります。
メルカリでは、タグ付き未使用品は新品、未使用でもタグを切ってしまうと新品ではなく、未使用品になってしまうので注意してください。
商品説明は詳しく記入する
メルカリでは商品を販売する際、商品説明文を記載する必要があります。
基本的には以下のような内容を記入します。
・商品コンディションの詳細
中古品の場合は、できるだけ具体的に状態を記載しましょう。
曖昧な記載をすると、返品を求められる場合もあります。
また、商品を購入した時期や使用頻度なども記載します。
説明書などがある場合には、同梱して発送する旨も記載しましょう。
・ブランド名や商品の詳細情報
商品ジャンルによっては、同じ商品名でも詳しいスペックが異なる場合があります。
特にパソコンやスマートフォンのジャンルは、詳しく書きましょう。
・その他注意点
大きな傷やタバコのニオイなどがある場合は、注意点として記載しましょう。
とくに喫煙環境で使用した商品は、自身では匂いに気づかない場合があるため注意してください。
メルカリの商品説明文の書き方が、その商品が売れるかどうかに大きく影響を与えます。メルカリでどのように説明文を書いたら売れるのかわからない人は、下記の記事を読んで悩みを解決しましょう。テンプレートもあるので参考にしてください。
例 衣類を出品する場合
たとえば、メルカリで衣類を出品する場合
・服のブランド
・素材や洗濯表示
・サイズ
・コンディション
・匂い
を商品説明に記入し、洋服の全体写真、タグの写真、(傷がある場合は)アップの写真を掲載しましょう。
メルカリで衣類を出品するときには、どんな写真を載せるかにより売れ行きが大きく変わります。以下の記事ではメルカリで売れるための写真の撮り方や、出品するときのコツや商品説明の例文を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【メルカリ例文】中古品を出品する際に、商品説明で使えるコメントなどのメルカリ定型文(テンプレート)

メルカリやオークションで中古品を販売する場合、新品の品以上に詳細なコンディション説明を記入する必要があります。
曖昧な表現や、実物と異なる内容をメルカリで記載するとトラブルの原因となりますので注意してください。ここではメルカリなどで中古品を売る際に使える商品説明の定型文を紹介します。
メルカリの商品説明の定型文の中に含めたい情報「使用頻度と購入日時」
メルカリなどで中古商品を出品する場合は、美品であっても使用頻度と購入した時期を記入しておくことをおすすめします。
購入したのはどのくらい前か、使用頻度はどのくらいか、把握している範囲で記入し、説明文があれば同梱しておくとよいでしょう。
また、電池などの消耗品を搭載している商品(PCやスマホ)に関しては、電池の消耗具合も記載しましょう。
メルカリの商品説明の定型文の中に含めたい情報「コンディション」
中古品と言っても、程度の良い「美品」から動作保証なしの「ジャンク品」まで、コンディションはさまざまです。
もちろんコンディションは良い状態の方が高く売れますが、状態を良く見せようと偽って出品すると、返品を求められる場合もあります。
また、そういったトラブルを起こすと、場合によってはメルカリのアカウントを停止される場合もありますので、商品コンディションは正しく記入しましょう。
メルカリで中古品を売る際のクレーム対応に向けた定型文の中でおすすめしたい商品説明の例文
メルカリで中古品の販売をする場合、コンディションを正確に記入していたとしてもクレームをつけてくる購入者も存在します。
その対策としては、
「中古品のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください」「中古品であることをご理解いただける方」などの注意書きをしておきましょう。
話し合いを行う上で、優位に話し合いを進めることができます。この注意書きはよく使うので定型文として準備しておくことをおすすめします。
もちろん、こちらに非がある際は返品に応じる必要がありますが、こちらに非がない場合にクレームを付けられた際は、メルカリのサポートセンターに相談しましょう。
メルカリに出品する場合の商品説明コメント定型文(テンプレート)の例文について

メルカリでは、商品1つ1つに商品説明欄が用意されています。
画像やタイトルだけでは伝えられない、詳しい商品情報やコンディションを記載しましょう。
記載する項目は
・商品名(詳しいスペック)
・使用頻度、購入日時
・商品の詳しい状態(コンディション)
・注意事項(大きな傷等がある場合)
上記の項目はあくまで一例ですが、メルカリに出す中古品の場合はできるだけ細かくコンディションを記入しましょう。
メルカリで記載した内容と実物のコンディションが異なると、返品を求められる場合もありますので慎重にチェックしましょう。
メルカリ出品物別の商品説明例文(定型文):ワンピース 新品
メルカリに「ワンピース 新品」を出品する場合の説明定型文の例文です。
新品未開封 タグ付きの商品です。
ペットなし、喫煙者はいません。部屋のクローゼットに保管していました。
1ヶ月前に正規店にて購入しましたが、着る機会がなくなったため出品します。
サイズはSサイズで、詳細はタグの写真からご確認ください。
購入した際のショッパーも残っていますので、そちらに入れて発送致します。
新品未開封品ではありますが、あくまでも一度人の手に渡っているお品ですので御理解の上ご購入ください。
新品であってもローブランドだったり、ブランド古着だけどメルカリで売れるか心配、という人には古着買取の利用がおすすめです。ブランド古着買取専門店【古着ブランドcom】はハイブランドに限らずローブランドの古着やアクセサリー、バッグ等も買取しています。送料・手数料無料の宅配買取があるので、自宅に居ながらすべてを終了出来てとても便利です。
メルカリ出品物別の商品説明例文(定型文):バッグ 中古品
メルカリに「バッグ 中古品」を出品する場合のコメント例文です。
1ヶ月ほど前に正規店にて購入し、2週間ほど使用しました。
丁寧に扱っていたため、中古品ではありますが、非常に綺麗なお品です。
サイズは〇〇センチ×〇〇センチ、マチは〇〇センチになります。
素人採寸のため、多少の誤差があります。
美品ではありますが、購入時より取っ手に小さな擦り傷があります。
傷の詳細は写真にてご確認ください。その他、目立つ傷などは見受けられません。
発送の際は、ビニール袋に入れ購入時に付いてきたショッパーで梱包し発送します。
美品ではありますが、実際に使用していたため、完璧な品を求める方は購入をお控えください。
中古品であることをご理解いただける方のみご購入ください。
メルカリで説明書などを同梱する場合のコメント定型文の例文・出品物別:電子レンジ 傷あり
「電子レンジ 傷あり」の商品をメルカリへ出品する際に、説明書などを同梱できる場合のコメント例文です。
3ヶ月前に購入し、2日に1回程度の頻度で使用していました。
本体付属品共に欠品なしです。
また、説明書、保証書、購入時のレシートも同梱して発送致します。
都内のビックカメラで新品を購入したので、〇〇年までの保証期間付きです。
商品に同梱した保証書とレシートがあれば、故障時でも保証期間内であれば無料で修理を受けられます。
比較的きれいなお品ですが、開口部の取っ手にこすり傷があります。
使用には問題ありませんが気になる方は購入をお控えくださるよう、お願い致します。
傷の詳細は画像より確認してください。これらの注意点をご理解いただける方のみご購入ください。
購入時のダンボール箱に説明書など同梱し商品を入れ、箱に伝票を直接貼っての発送となります。
メルカリ出品物別の商品説明例文(定型文):例 BVLGARI 財布
「BVLGARI 財布」をメルカリへ出品する場合のコメント例文です。
BVLGARI 財布
〇〇シリーズ シリアル番号は〇〇になります。
購入時に付いてきた外箱や袋、ショッパーは付属しません。
防水のためビニール袋に入れてから発送致します。
1年ほど前に都内の正規店で購入し、半年間使用しました。
半年間使用したお品ですので、多少の使用感が見られます。
特に、小銭入れの内側に革の剥れが目立ちます。
詳細は画像2枚目を確認してください。
半年間はペットなし、喫煙者なしの環境で保管していました。
中古品ですので、完璧な品を求める方は購入をお控えください。
以上をご理解いただける方のみご購入ください。
今まで使っていたブランド品をメルカリへ出品したら、新しいブランド品を手に入れたくなりますね。海外ブランドファッション通販AXES(アクセス)では、会員登録でもらえるクーポンやボーナスクーポンが用意されていてお得がいっぱいです。30日間の返品保証も付いているので安心してお買い物が出来ます。
メルカリで出品に使えるコメント定型文(テンプレート)の例文

メルカリとは個人間取引を仲介しているサービスです。
そのためメルカリで取引をするには、値段設定から値引き交渉までを個人間で行う必要があります。
メルカリではコメント欄やメッセージで購入者とやりとりをして、スムーズな取引を行いましょう。
次項からはメルカリで商品を出品する流れに沿って、実際のコメント例文を紹介していきます。
メルカリでの値下げ交渉に対応する時の定型文
ここではメルカリで出品中の商品に対する、値下げ交渉対応への例文について紹介します。
相手の提示した金額で販売してもいい場合は、
「コメントありがとうございます。ご提示の金額に修正致しますので、購入をよろしくお願い致します。」といった定型文で、了承した旨を伝えましょう。
提示された金額で販売できない場合は、
「コメントありがとうございます。申し訳ありませんが、ご提示の金額では難しいです。」といったメッセージを送りましょう。
メルカリの場合、コメント欄でのやりとりは他の利用者も閲覧できますので、コメントには丁寧に対応しましょう。
また、あまりに非常識なコメントなど、閲覧する方が不快に感じるような場合は、メッセージを削除することをおすすめします。
嫌な思いをするような値下げ交渉は、回避できるのが一番です。以下の記事ではメルカリのプロフィール、商品タイトル、商品説明文を上手く使うことで不要なトラブルが起きないようにする方法やコメントへの対処法を紹介しています。テンプレート文もありますので、ぜひ参考にしてください。
参考:メルカリはプロフィールの活用でトラブル対策を!例文も紹介
メルカリで購入された場合のメッセージの定型文
メルカリで商品が売れ、購入者の支払いが済んだ場合、発送予定を伝えるコメントを送りましょう。
例文として、
「ご購入、お支払いありがとうございました。商品は〇〇日以内に発送致しますので、今しばらくお待ちください。」のように、発送がいつになるのか具体的に伝えると、取引相手も安心できます。
メルカリで支払期日をリマインドする際の定型文
メルカリで商品が売れた場合、購入者の支払方法によっては、支払いが行われるまでに数日かかる場合があります。
特にコンビニ支払いの場合、期日ぎりぎりまで支払を行わないメルカリ購入者も存在します。
そんな場合には、
「ご購入いただいた商品の支払期日が迫っておりますが、支払予定を確認させていただいてよろしいでしょうか?」といった定型文でメッセージを送りましょう。
また、購入完了日からは取引画面より、キャンセル申請と購入者の違反報告を行うことができます。
単に支払を忘れているだけの方もいますので、支払期日が近づいたら、上記例文のようなメッセージを送りリマインドしておきましょう。
メルカリで商品発送時に連絡をする時の定型文
メルカリでは購入者の支払が確認できた後、商品を発送します。
また、商品を発送した後は購入者へ発送完了メッセージを送りましょう。
例文としては「先程〇〇(発送方法)にて、発送いたしました。到着まで今しばらくお待ちください」といった定型文でメッセージを送りましょう。
メルカリ便の場合は自動で追跡番号が伝えられますが、メルカリ便以外の発送方法を選択した場合は、追跡番号も記載してください。
メルカリで購入者を評価する時の定型文
発送後、メルカリ購入者から受け取り評価がされると、あとは購入者への評価をすれば取引完了となります。
メルカリの場合、購入者を評価する際にコメントの入力が可能となっています。
購入者との取引に不満がなかった場合は、可能な限りコメントを記入しましょう。
内容としては、「この度は商品を購入していただきありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。」といった短文のコメントで構いません。
システム上は無言評価もできますが、一言コメントを記入するだけで取引相手も心地よく取引を終えることができます。
メルカリを使う上での注意点

次項からは実際にメルカリを使う上で、注意すべき点について紹介していきます。
また、メッセージのテンプレートもあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
メルカリで発送時のメッセージ定型文
メッセージを送るのが手間だという方でも、最低限、発送時のメッセージだけは送るようにしましょう。
いつ発送されたのかわからないと、購入者は非常に不安に思います。
メルカリ購入者によってはメッセージを一度も送らない場合、受取評価を下げられてしまうことがあります。
以下ではメルカリ便を利用しない場合の例を紹介します。
例 メルカリ便以外で追跡番号がある場合
「先程〇〇より発送致しました。追跡番号は〇〇になります。
到着までは○日程度の予定です。到着までしばらくお待ち下さい。
商品確認ができましたら、受取評価をよろしくお願い致します。」
例 メルカリ便以外で発送した場合(追跡番号なし)
「先程〇〇より発送致しました。追跡番号はございません。
到着までは○日程度の予定です。到着までしばらくお待ち下さい。
商品確認ができましたら、受取評価をよろしくお願い致します。」
到着までの日数は、多くの場合配達員の方から伝えられます。
もしわからない場合は記載しなくても構いません。
商品を発送する際に一緒にお礼の手紙を入れることで、購入者も気持ちよく商品を受け取れます。お礼の手紙により購入者が好印象を受けることは自分への高評価に繋がりますので、手紙を入れる事をおすすめします。
どんな文章を書けばよいのかわからない人は手紙の書き方や例文を紹介していますので、以下の記事を参考にしてください。
参考:【メルカリ出品者必見】お礼メッセージの例文と書き方を紹介!
メルカリでは独自ルールは違反
メルカリで出品されている商品の中には
・即購入禁止
・プロフィール参照必須
・専用出品
・ノークレームノーリターン
といった、独自のルールを定めている場合があります。
しかし、メルカリの規約ではこのような独自のルールを禁止しています。
独自に決めたルールを破ったことを理由とした、返金拒否や販売後のキャンセルはできません。
もしもキャンセルを行ったり、返金を渋ったりしてしまうと、最悪の場合アカウントの停止処分となります。
トラブルの元になりますので、きちんと規約に則って出品するようにしましょう。
商品を購入する場合
今回は出品時の定型文に重点を置いて解説してきましたが、メルカリを利用していれば商品を購入する機会も訪れるでしょう。この場合も販売時と同様に、丁寧で迅速なメッセージを心がけていればトラブルが起きることはまずありません。
ただ1つ注意していただきたいのが、コンビニ払いとATM払いを選択した決済の場合です。メルカリでの支払いには期限があり、「購入日を含む3日目の23:59:59まで」と定められています。
「支払期日をリマインドする」で説明した通り、この支払い期限を過ぎると出品者はキャンセル申請と購入者の違反報告を行うことが可能になります。そうなると最悪、自分のアカウントに利用制限がかかる場合があるのです。
「中々時間が取れずに後回しにしていたら支払いを忘れてしまった」という場合、思いがけずアカウント利用停止となってしまうことがあるので注意してください。![]()
メルカリ出品での商品説明文やコメント定型文(テンプレート)の例文まとめ

いかがでしたでしょうか?
メルカリでは、商品紹介文を曖昧に書いてしまうと、トラブルのもととなります。返品トラブルやクレームを未然に防ぐためにも、例文を参考にしながら同梱するものや、商品の説明はきちんと記載しましょう。
メルカリ購入者は販売者の取引評価を見て購入する場合も多く、「良い」の評価をしてもらうためにも、メルカリ購入者からのコメントや質問には丁寧な対応を心がけましょう。
ところで、ビジネスで成功するためには独学よりも体系化された教材やサービスを活用して学ぶ方が結果が早く出ます。
ここではアクシグ編集部が予め登録した上で責任者に直接取材をし、有用性を確認した教材やサービスのみを厳選してご紹介します。無料ですのでお気軽にご登録またはご相談ください。
【限定公開】成功者続出の秘密のノウハウ

日本未上陸のノウハウで先行者利益が得られる大チャンス到来!
日本ではまだ知られていない秘密の情報をお届けします。
あなたのビジネスを成功させるために、今すぐ限定情報を入手してください。
【無料相談】Biz English

ビジネス英語は3ヶ月でマスターできます!
インターネットの買い物に慣れてくると、アメリカのアマゾンやeBayで購入したり出品したりしたくなるでしょう。英語ができなくてもGoogle翻訳やDeepLなどのツールを使えば始めるのは簡単です。
ところがクレームや返金などが発生すると機械翻訳では上手く交渉できません。金額が大きくなりビジネスレベルになるとなおさらリスクが高くなります。
ビズイングリッシュはビジネス英語専門の英会話スクールです。受講生は全くのゼロから英語でアカウントを復活させたり、海外の展示会で交渉に成功したりと幅広く活躍をしています!
今すぐビジネスレベルの英語力を身につけましょう!